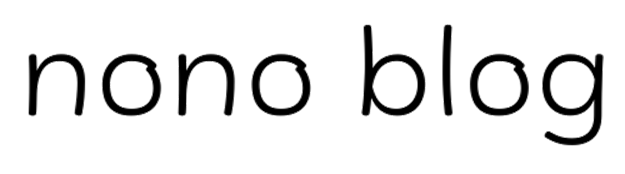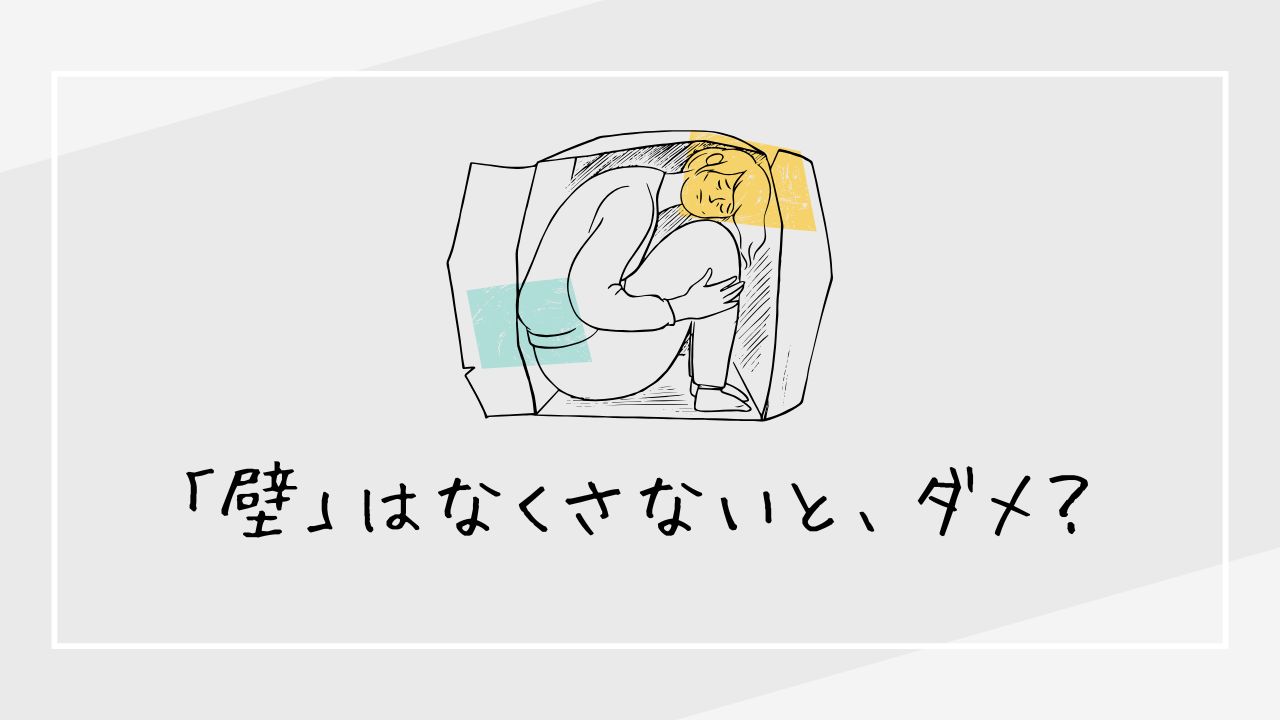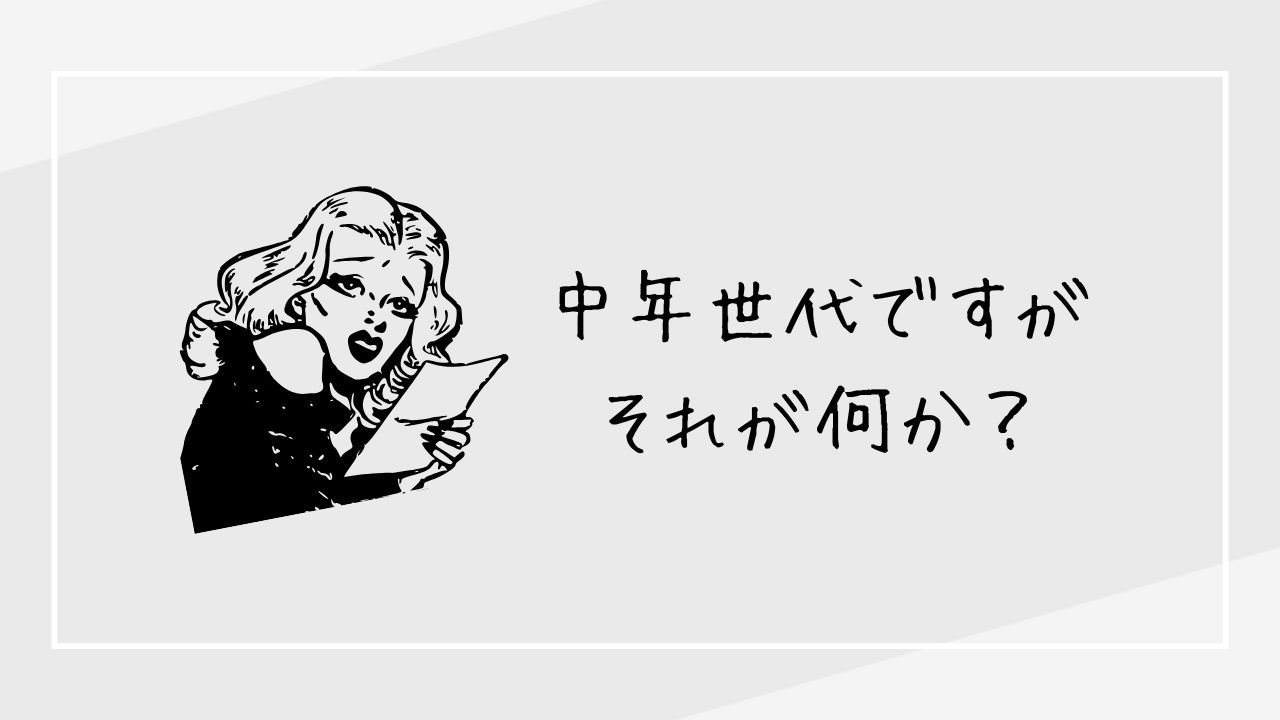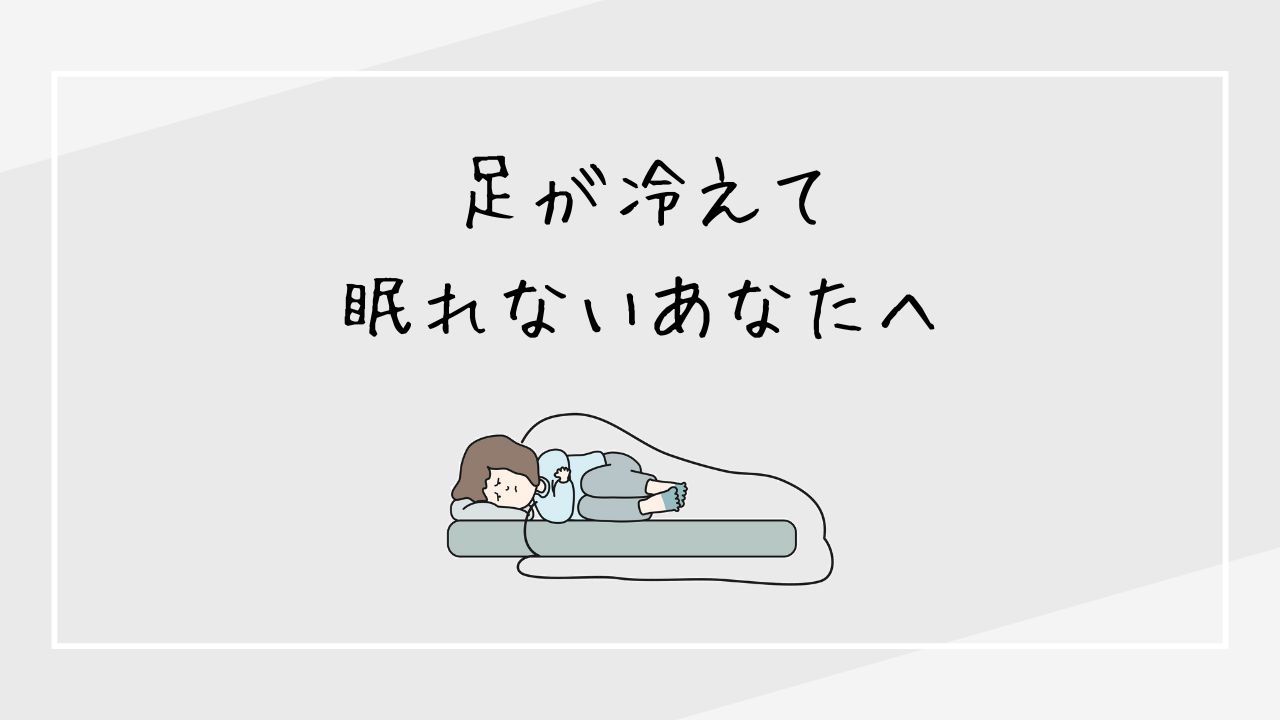SNSで積極的に自分をオープンにしている人たちを見ると、「すごいなぁ」っていつも思うんです。
「自己開示しよう」「もっとオープンに人と関わろう」「壁なんてない方がいい」
巷ではそんな言葉が飛び交うけれど、正直、私はそれがちょっと苦手です。
心の奥底にそっと閉まっておきたいこと、誰にも触れられたくない領域。オープンにできる人が羨ましいけれど、どうしても一歩踏み出せない自分もいるんですよね~。
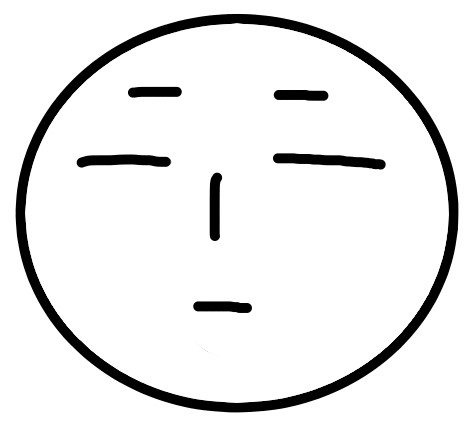
だーれも、そんなあなたのこと気にしてないし、見てへんで。

ええ、自意識過剰だって分かってますけどね(笑)
それに、自己開示してしまえば「あれ?こんなん?」って拍子抜けすることでしょう。頭ではそう理解しているのに、心のブレーキがどうしても外れない。
こんなふうに思ったこと、ありませんか?
- 自己開示ができない
- 人との間に壁を感じる
- それがダメなことだと感じてしまう
私自身も、そんな思いを抱えてきました。
けれど、ある1冊の本が、長年抱えていた「自己開示できない自分」への罪悪感を、ふっと軽くしてくれたんです。それがこちら。
『壁はいらない、って言われても。』今中博之 著
壁があってもいいと、許し合える仲間と環境
著者の今中さんは、知的障がいのあるアーティストたちが創作活動を行うアトリエ「インカーブ」を設立し、ご自身も下肢に障がいを抱えています。
本書には、そんな今中さんの体験談や、アーティストたちとの関わりを通して日々感じたことが独特な視点で綴られています。その内容は、私の心に深く、深く突き刺さりました。
印象的だったのは、アトリエ「インカーブ」には、自分の作品を他人に見せることや販売することを頑なに拒むアーティストがいるというエピソードでした。
内容を知ろうと問いかけても、彼らは決して口を開かない。ただ、作りたい時に作り、手を止めたい時は止める。それは「好きなように生きている」姿そのもの。

それが許される環境だからじゃない?
「許される」というより、お互いが許し合っているんですね。著者は、こう言います。
大切なことは語らず、胸の奥底にしまっておけばいいと許しあえる仲間だったから。
引用:「壁はいらない、って言われても」
それを読んだとき、私は思ったんです。

「ああ、壁があってもいいって、こういうことなんだ」と。
こんな環境も素敵だなって思いませんか?
すべてをさらけ出すことだけが、幸せじゃない
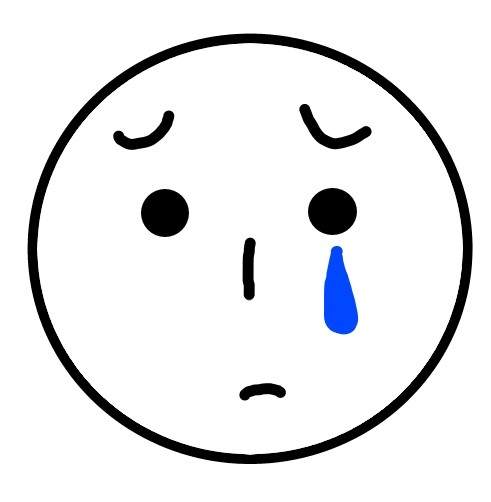
私のまわりの環境は、そうじゃないし。
私たちの現実では、必ずしも「許し合える」仲間や環境ばかりではないかもしれません。
それでも、まず知っておきたいのは、そんな世界が存在するということ。
よく言われますよね。
「壁をなくして素直になろう」「弱さを見せよう」
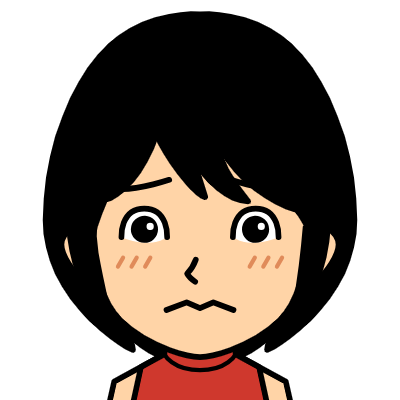
それができる人はいい。でも、できない人もいるのに~。
と、よく拗ねていた私(笑)。うまくできなくて、自己嫌悪になったこともあります。
そんなとき、この一文に救われました。
心のバリアフリーになることだけが、幸せになる行為ではない。(中略)つながりすぎず、いつも逃げ道を作っておく。体の一部、心の一部だけを解放し、全部をさらけ出す必要なんてない
引用:「壁はいらない、って言われても」
「壁は、なくさなければいけないもの」と思っていた私にとって、この視点は大きな転換でした。
つまり壁は、「人を拒むためのもの」ではなく、「自分を心のバランスを守るためのもの、整えるためのもの」だととらえ、だから「壁はあってもいい」と、私は解釈しました。
そうしたら、自己開示できないことが、「問題」ではなくなったんです。
自己開示してもいいと思えるような状態、「できない」じゃなくて「しない」以上!
そもそも、このアトリエ「インカーブ」のアーティストたちは、壁があることを問題にはしていません。
「壁がなくせない・・・」と思うから問題なのであって、「壁が必要、あってもいい」と思えたなら、それは問題じゃなくなりますよね?
たとえば、こうとらえてみたら、どうでしょう。
私は「自己開示しません」。それが何か?
私はミステリアスな女(男)なんです。文句ある?
そんなふうに、ちょっと開き直ってみる。それくらいのスタンスで、ちょうどいいのかもしれません。

壁があってもなくても、元気に過ごしていいし、幸せになってもいい。いや、なれるし。
大事なのは「壁をなくすこと」じゃなくて、「壁があってもいい」と思える状態を先につくること。
その先に、ふっと思えるかもしれない。
「あ、自己開示してもいいかな」

「自己開示しなきゃ~」ではなく、「してもいいかな」とそう自然に思えたときがグットタイミング。
無理に開く必要はない。開きたいと少しずつでいいんですよ~。
まとめ
- 壁があっても、人とつながることはできる
- 「壁をなくさなきゃ」と思うことが苦しみを生む。「壁があってもいい」と思えたなら、それはもう問題ではない。
- 「自己開示できない」んじゃなくて「しない」と捉えてみるのも面白い
- 「自己開示してもいいかな」と思える準備が整ったら、自然にできる