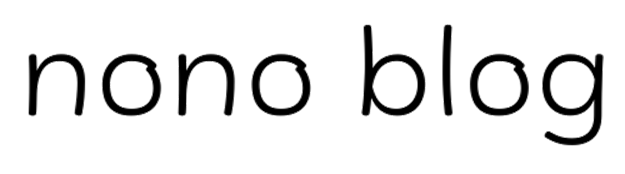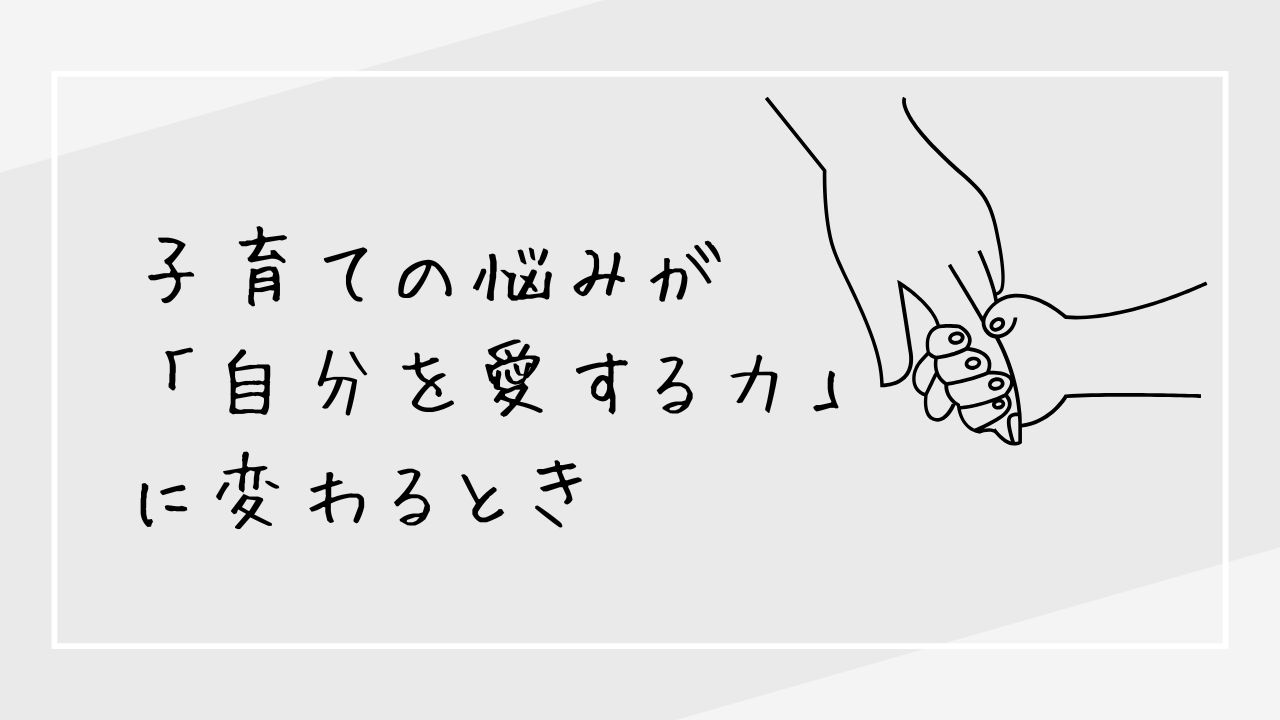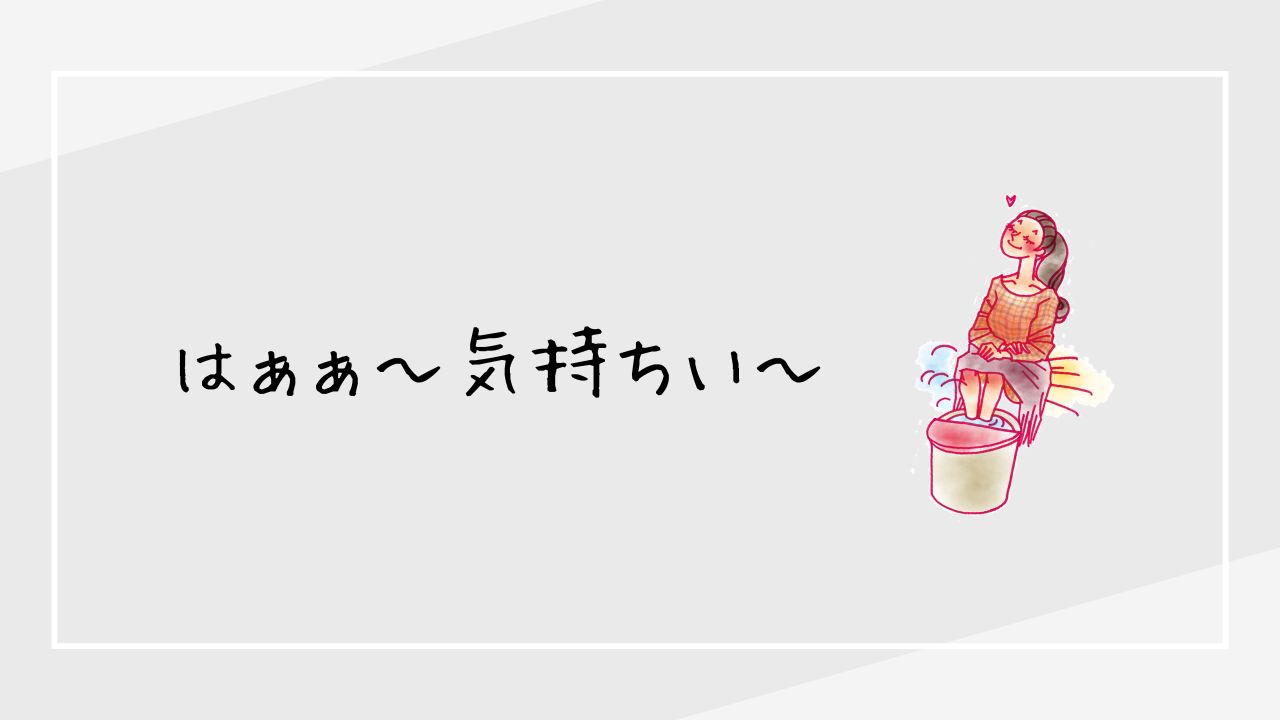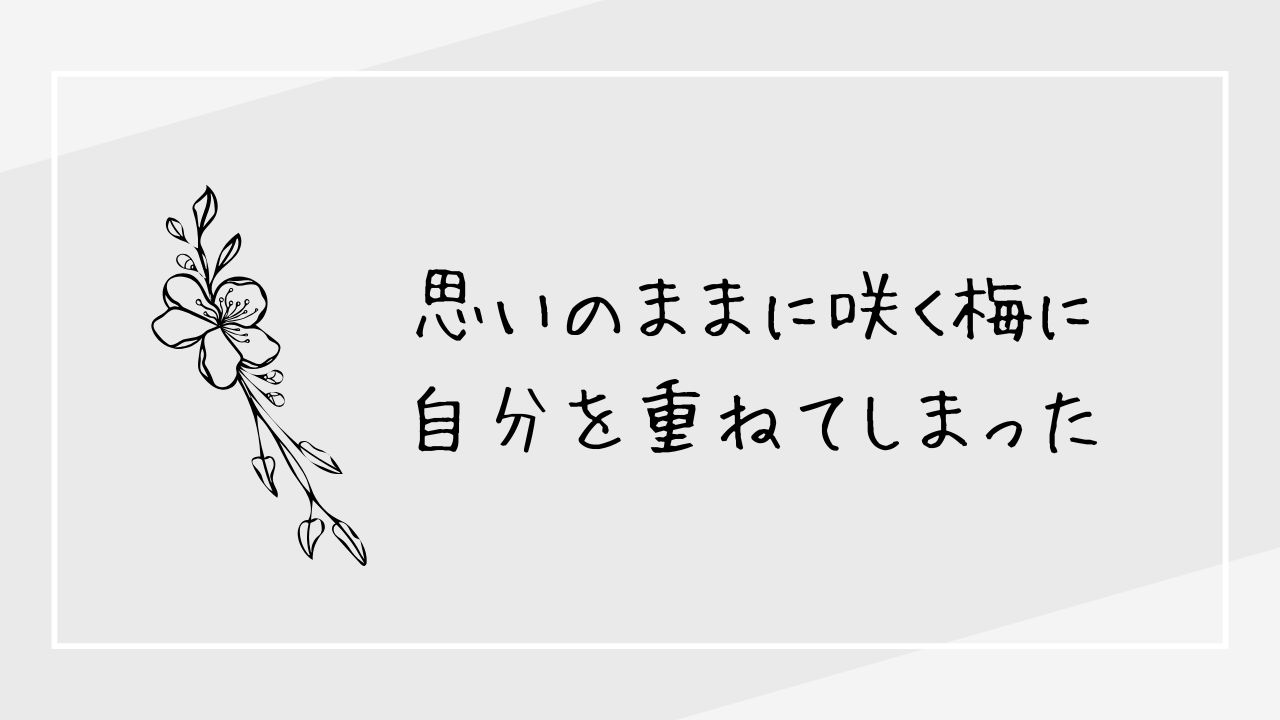「あーあ、なんで私の子育てはうまくいかないんだろう・・・。」と、よその子と比べて落ち込んだり、「私の育て方が悪かったんだ」と自分を責めてしまったり。
そんなふうに悩んだこと、きっとあなたにもあるのではないでしょうか。
私もそうでした。
「もっとああしてあげればよかった」と思い出すたびに胸が締め付けられ、今でも涙がこぼれることも少なくありません。
でも同時に、少しずつではありますが「あのときはあれで精一杯やっていたんだ」と思えるようにもなってたんです。
子どもが生まれたその瞬間から完璧な「母」になれるわけじゃなく、いろんな葛藤があって、たくさん悩んで、たくさん泣いて、今だからこそ気づけること、思えることがあるんです。
そうやって少しずつ、人は「母」になっていくんだなと実感しています。
そんな苦悩な子育て時代にたくさんの子育て本を読みあさりました。

特に私の心に深く響き、大きな影響を与えてくれたのが、児童精神科医・佐々木正美氏の著書でした。
子育てに悩むあなたに、私は心から佐々木氏の言葉を届けたい。 佐々木氏の教えは、子育てに限らず、あらゆる人間関係、そして何より自分自身との向き合い方にも通じる大切な気づきを与えてくれました。 私の経験が、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
子育ては、究極の「自分と向き合う」時間
子育てほど、自分自身の心のクセや価値観と向き合わされるものって、ないんじゃないかと思うんです。
「他人は変えられない」とはよく言いますが、なぜか我が子だけは「変えられる」と思っていました。いや、正直に言えば、私の思う通りの人間に育てなきゃと思い込んでいたんですよね。
それは、子育てという名のもとに、我が子をコントロールしていたんです。なぜなら、子どもの評価がそのまま母としての自分の評価だと勘違いしていたから。

良くも悪くも「子ども=私の映し鏡」と感じていたんですよね。
妊娠がわかったとき、「無事に産まれますように・・・」と、ただそれだけを願っていました。
誕生したとき、「この子が幸せな人生を歩みますように」って、心から祈るような気持ちでした。
ところが成長するにつれて「あれができた方がいい」「こう育ってくれたら安心」「こうしないと困る」と、気づけばいろんな条件をつけてしまっていました。まるで、その通りにならないと愛せないかのように…。
そうなると、当然うまくいかないことも増えてきて、思い通りにならない子どもにイライラして悩むわけですよ。なんでこうなるの? 私の育て方の何がだめなの?って・・・。
育てられたようにしか、育てられない
子どもが幼かった頃、ある年配の方からこんな言葉をかけられたのを今でも覚えています。
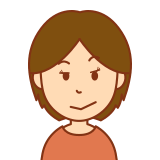
育てられたようにしか、育てられないのよ
子育てがうまくいかないとき、私はこの言葉を思い出し、「ああ、私はこんなふうに育てられたんだな・・・。じゃあ、どうすればいいの?」って途方に暮れていたときに出会ったのが、児童精神科医の佐々木正美氏の本でした。
佐々木氏の著書は、どれもこれも本当に優しい言葉が詰まっていて、私の子育て観が少しずつ変わっていったんです。
上記以外にもたくさんの著書があり、むさぼるように次から次へと読みまくっていました。
そして、これらの本を読み進めるうちに、「子育てを思い通りにしよう」という考え自体が、そもそも大きな勘違いだったことに気づかされたんです。
佐々木正美氏の子育て論:子どもが望む親とは
佐々木氏が何よりも大切にされていたのは、親の思う通りに子育てするのではなく、子どもが望む親であること、子どもが愛してほしい愛し方で愛してあげることでした。
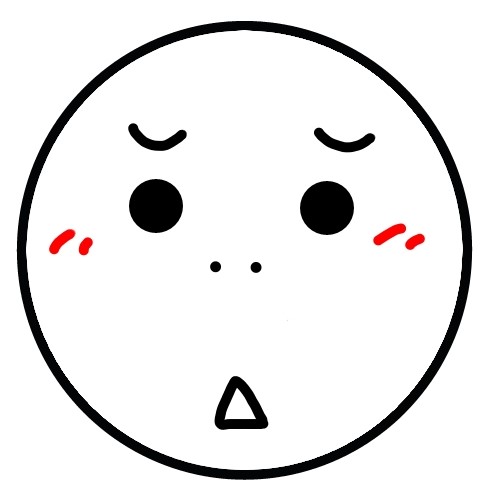
それ、難しくないか
そーなんです。難しいんです。

私だって自分が欲しかった愛し方で愛してもらえなかったし・・・
あれだめ、これだめ。それ危ない。こうしなさいと、厳しい母でした。でも、今ならわかります。
母もまた、母の欲しかった愛で育てられなかったんだな、と。だから、しょうがないよなって。
子どもが「〇〇して」という理由
佐々木さんの子育て論は、ある意味とても理想的に聞こえるかもしれません。でも、他のどんな子育て本より心に響きまくりました。
佐々木さんの考え方で特に衝撃だったのがこちら。
子どもの要求を聞く前に、親の要求を聞かそうとするから、子どもは親の言うことを聞かなくなる
子どもは、ただ「言うことを聞かせる対象」じゃない。
「自分の思いを聞いてくれる存在」として、親を求めている。
それに、これは子育てだけでなく、どんな人間関係にも通じることだと思いませんか?
誰かが自分をコントロールしようとしていると感じたら、どんなに正しいことでも、人は聞きたくなくなるものです。伝わってくるのは、話の内容よりも「コントロールされている」という感情だけ。
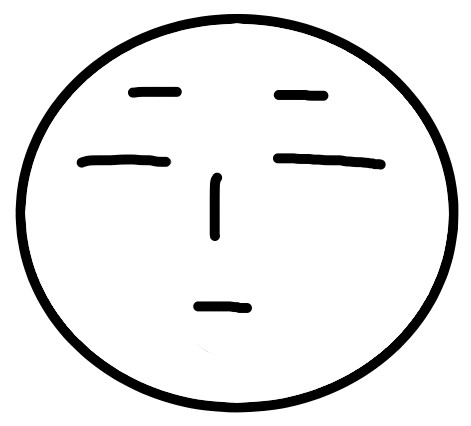
親子といえども「人間関係」だもんね。
そして、佐々木氏はこう言うんです。
子どもが「〇〇して」と言うのは、自分でできないからではなく、お母さんが自分のために動いてくれるということに、こだわっている。(もちろん子どもは無意識にですよ)
お母さんが子どものためにいろいろやってあげていると思っていたとしても、子どもにとってはそれでも足りないんだと・・・。
「泣けば買ってもらえる」と思ってるわけじゃなかった
子どもが「あれ欲しい」「これ買って」と泣くとき、私はよくこう思っていました。

泣けば買ってもらえると思っているんだろう~
でも、佐々木氏は、こう説明します。
その子が泣くのは、これが欲しいからではない。お母さんに自分の言うことをもっと聞いてほしいということなのです。
でも親は、子どもの要望を何でもかんでも聞いていたら、わがままな子になるんじゃないかと心配するでしょ。
そんな親の不安に、佐々木氏はこう言います。
どんな子も、親が手をかけるときがある。かけなきゃいけない。満足すれば言わなくなる。手をかければかけるほど、それだけの成果を見せてくれる子だと思ってください。
「手をかけなきゃいけない時がある」なんて、今まで考えたこともなかった。
一見、聞き分けが良くわがままを言わない子が、いい子育てをしている実感につながりやすいですよね。
でも「手をかける時がある」という言葉は、子育てで悩んでいた私に「別にそれは問題じゃない」と言われているような気がして、心の底からホッとしたのを覚えています。
「もっと過保護になっていい」──過保護と過干渉の違い
佐々木氏は、言うんです。もっと「過保護」になれと。
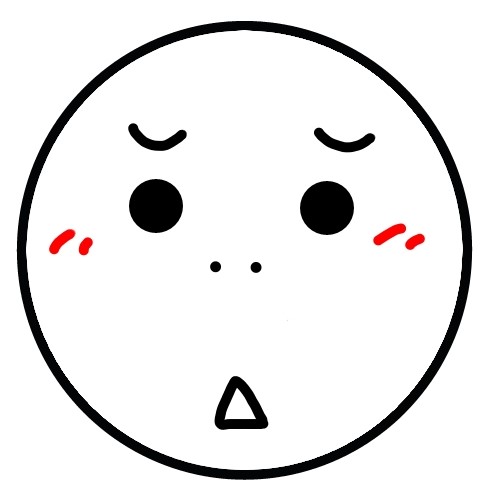
それは、あかんやろ

「過保護」と「過干渉」は違うのだと言います。
過保護は、子どもがやってほしいことをやりすぎること。
過干渉は、子どもがやってほしくないことをやりすぎること。
今の親は、過保護ではなく「過干渉」になりがち。だから、子どもがやってほしいことをやりすぎるぐらいがちょうどいい。それが「もっと過保護になれ」という言葉の真意だったんですね。
そして、どんなことも、その子のできるタイミングがあるからそれを信じて待ってあげてくださいと。
お母さんもお母さんのままでいい
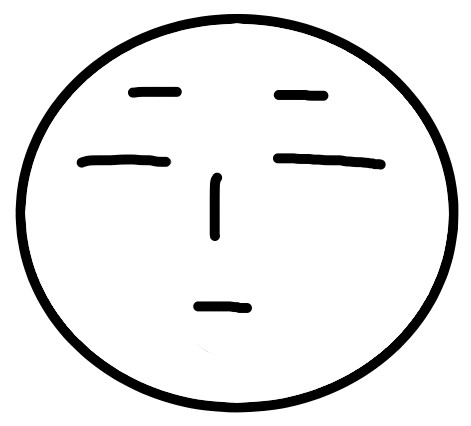
なんかすごく理想論に聞こえてきた。
でもね、佐々木氏の子育て論は、子育てだけに限らず全ての人間関係や、自分との向き合い方にだって通じるものだと思えるんです。

想像してみてください。
もしあなたが、自分が欲しい愛し方で親や周りの人から愛されたとしたら?
もしあなたが、できないことがあっても、できるまで待つよと言われたら?
もしあなたの要望を真っ先にたくさん聞いてもらえたら?
どんな気持ちになりますか? 超心地よくないですか?
それは子どもであろうが、大人であろうが、関係ないですよね。
私が欲しかった愛され方は、コントロールされる愛され方じゃない。
もっと私の思いを聞いてほしかった。否定しないでそのままでいいよって言ってほしかった。
結局、佐々木氏の教えは、自分がやってほしかったこと、自分がしてほしかった愛し方を子どもではなく、私が私自身にまずはやってあげればいいんだ、ということに気づきました。
つまり、私がそうできるまで、私が私を待ってあげる。
そして、佐々木氏は、こう言います。
「わが子をそのままでいいと認めることは、お母さん自身もそのままでいいと認めることに繋がる」
逆に言えば、思うようにできないい子育てをそれでいいと認めることは(待ってあげることは)、わが子や他者に対しても、それでいいんだと(待ってあげる)ことにも繋がる。
できないときもあるし、うまくいかない日もある。でもそんな自分も含めて「いいんだよ」と言ってあげたい。子育ては自分育て。一緒に育っているんですよね。
まとめ
- 子育ては、自分と向き合わざるを得ない自分育て
- 親が望む子に育てるのではなく、子どもが望む親を目指してみよう
- どんな子も、親が手をかけるときがある。かけなきゃいけない
- もっと「過保護」でいい。やりすぎていいこともある
- 子どものタイミングを信じて、待つことも目指してみよう
- 我が子をそのままでいいと認めることは、親自身もそれでいいと認めることになる。
逆もしかり。

悩んでいるときはしんどいけど、悩むというのはそこに「愛があるからだ~」と、世界の中心で叫びたい思いです!