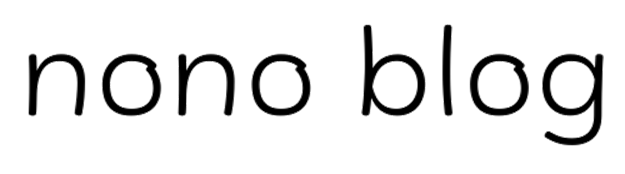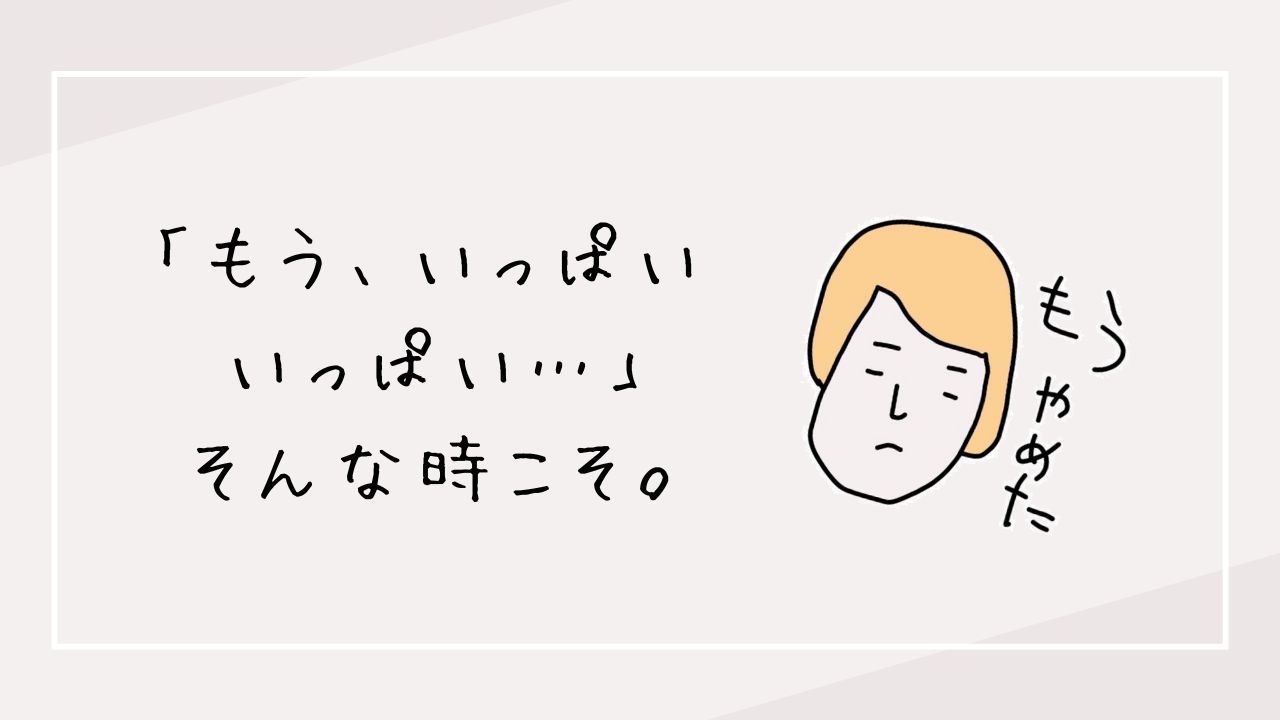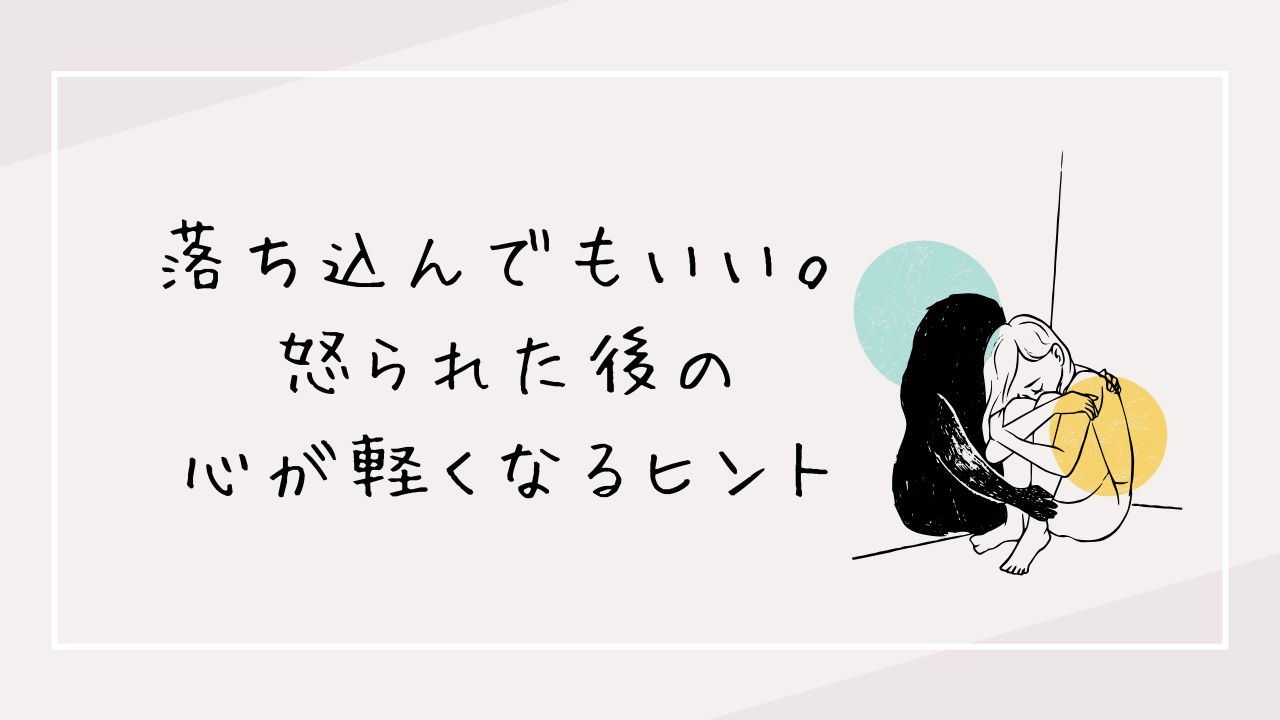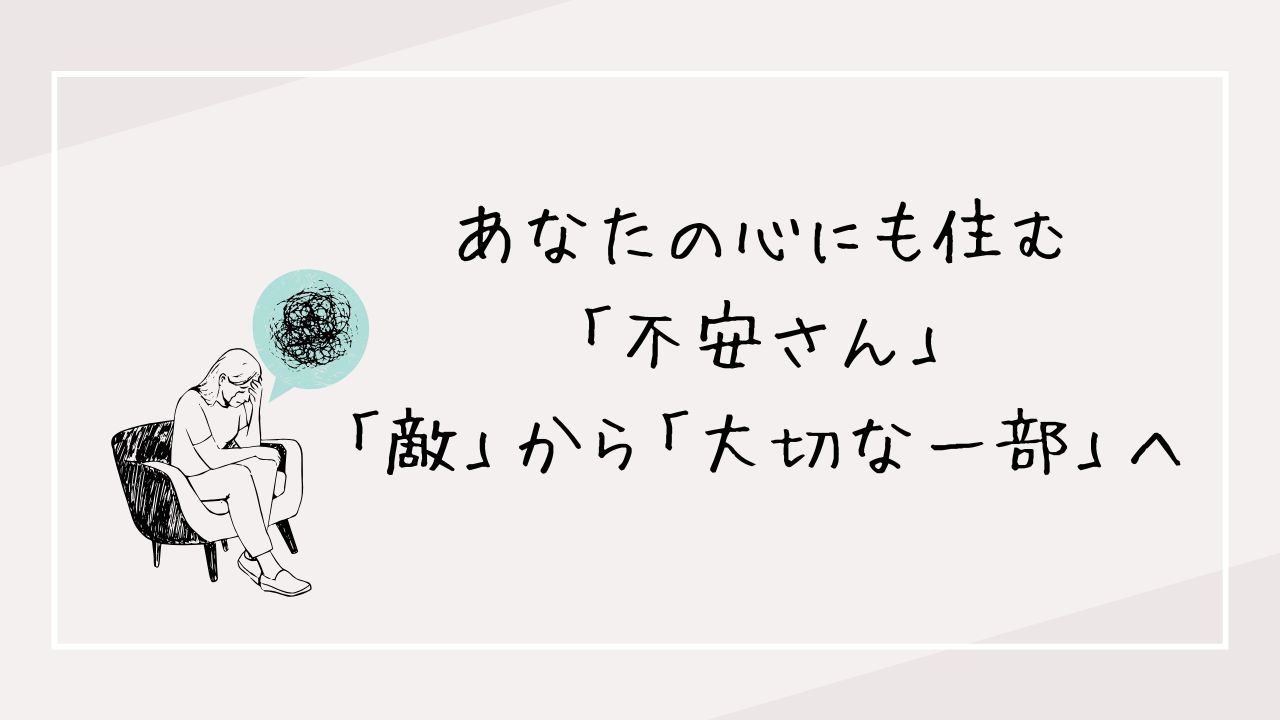幼い頃から教え込まれた「石の上にも三年」「継続は力なり」と、「続ける」ことの大切さ。
好きで始めたはずのことさえ、途中で飽きてしまったり、心が悲鳴を上げているのに「続けるべき」という呪縛に苦しみ、そんな自分を責めてしまったり。
美徳とされる「続ける」ことの裏で、私たちはいつの間にか「やめる」ことを悪だと捉えるようになっていませんか?

ちなみに、私は「やめる」のが超苦手です・・・。
こんな本を、読みました。
これらの著書をヒントに、「やめる」ことに対するネガティブな感情を私の解釈も含めて語ってみました~。よろしくっ!
カルチャーショック!「やめる練習」をしてきたマレーシア人の生き方
『日本人は「やめる練習」がたりてない』 野本 響子 著
著者の野本さんは、お子さんの登校しぶりをきっかけに出会ったマレーシア人家族の考え方に惹かれ、なんとマレーシアに移住してしまったお方なんです。
そこで目の当たりにしたのは、日本の常識とはまったく違った彼らの人生観にカルチャーショックをうけまくったといいます。
マレーシア人の思考
・ハッピーじゃないなら、居場所を変える。
・イヤなら、やめる。
・「やめる」は挑戦と失敗の繰り返し。だから罪悪感なんてない。
つまり、マレーシア人にとって小さい頃から「やめる練習」を何度も体験しているので、「やめる」は、より良い未来へのステップ。悩むこと自体が不思議なんだそうです。
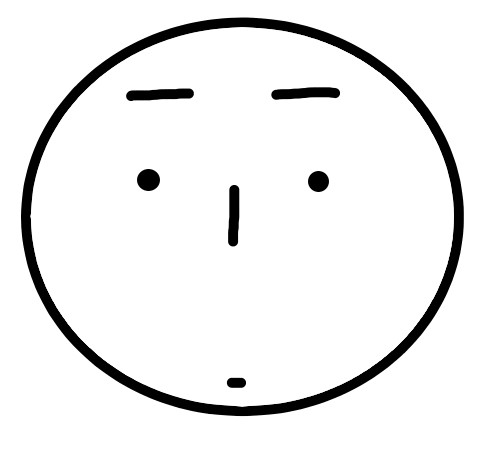
イヤなら、やめりゃーいいじゃん。なぜ悩む?
「我慢こそ美徳」?私たちが「やめる」を恐れる理由
一方、私たち日本人は、マレーシア人のように簡単にやめることがなかなかできなくないです?
それは、なぜか。
著者は、こう言います。
続けることを美徳とし、小さい頃から「我慢する練習」を叩き込まれてきたからだと。

私は「我慢する練習」をしまくってました~。
日本人の思考
・続けることでいつか報われる。
・努力は必ず実を結ぶ。
・やめることは根性がない証拠。
もちろん、「続ける」ことで得られる成長はあります。だから我慢も努力ととらえ、いつか報われる。そんな成功話や根性論も好きですよね。
しかし、「続けることだけが正しい」という考え方は、「やめる」という選択肢に大きな罪悪感を生み出します。

それは、幼い頃から積み重ねてきた「我慢の練習」が、「やめることへの恐怖」も同時に植え付けてきた、とも言えないでしょうか。
「やめる」は逃げじゃない!自分と他者への優しさという視点
著者のご家族はマレーシアに移住後、あれほど日本では登校しぶりをしていたお子さんも、インターナショナルスクールに通いはじめ、みるみる元気になっていったそうです。
マレーシアでは、学校を変えることは日本ほど大変ではなく「子どもがハッピーじゃないなら、すぐにやめて次を探す」んだそう。
合わない環境から離れることは、決して「逃げ」とはとらえず、むしろ、自分自身を守り、可能性を広げるための賢明な選択なんだという価値観です。
そういうマレーシア人の人生観は、他者への「いいかげんさ」にも寛大で、怒ったりクレームをいう人も少ないらしいんですね。

それって、「自分にも他者にも優しい社会」なんだなと、読んでて思いました。
「もったいない」の裏側。「やめる」決断を鈍らせる心理
何かを続けるには、どうしても我慢や努力が伴いますよね。でも「やめる」ことを「逃げ」だと捉えていると、自分にも他人にも厳しくなってしまう。
そして、続けられないと「根性がない」「ダメなやつだ」なんてレッテルを貼ってしまう。だから、本当はもう限界なのに、無理をして「続ける」ことを選んでしまう…。
だからこそ、著者は、私たちはもっと幼い頃から「やめる練習」は必要だと主張しているんです。

続けることを頑張ってる人ほど、他者にもそれを求めるしね~。
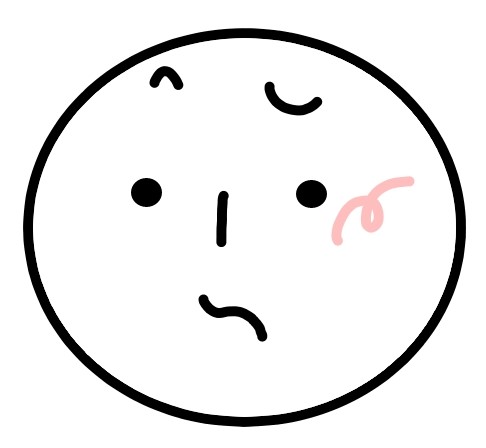
そうはいっても、今まで頑張って続けてきたのに途中でやめるなんて、なんかもったいないよな~。
そんな思いに対して、以下の著書にとても参考になることが書かれていました。
『ストレスの9割は「脳の錯覚」』 和田秀樹 著
この本の著者は、私たちにはさまざまな思い込み「脳の錯覚」を持っていると言います。
「お金と時間をかけてやってきたことを今更やめられない」「やめるのがもったいない」。
そう考えてなかなか「やめる」決断ができないのも「脳の錯覚」であり「コンコルド効果」と呼ばれる心理現象なんだそうです。
特に日本人は「逃げる選択肢をとりたがらない」と言います。そして

やめるのが超苦手な私にとって
著者のこんな言葉が、グサっと刺さりました。
幸せになるにはこの道しかない、と思い込んでいる人よりも、「こんな道もある、あんな道もある」と、いろんな道を探せる人のほうが、ラクに生きられます。
(中略)
「幸せになれるなら、どんな道でもいい」と思えたら、いくらでも道は探せます。逆に、それができないと、エリートでさえ生きるすべを失ってしまうのです。
どうです?とても重みのある言葉だと思いませんか?
私はこの言葉に、
「やめたら、どんな怖いことが起こると思っている?」
「どんなことを感じるのが嫌だと思っている?」
「やめることに対して、どんな前提を持っている」
その前提、思い込みを疑ってみる。
そして「どんな道でも幸せになれるとしたら?」「本当はどうしたい?」
そこに意識を向けてみないかって著者からメッセージを受け取りました。
本当はどちらでもいい。「やめる」に対しての前提をニュートラルに
大切なのは、「やめる」ことが常にネガティブな選択肢ではないということ。
「続ける」ことにも、「やめる」ことにも、メリットとデメリットがあります。本来はどちらも「ただの選択」であり、どっちでもいいんですよね。
でも「続けることが大事」「今まで頑張ってきたんだから」という思考に偏っていると、たとえ「やめる」という決断をしたとしても、心のどこかで続けられなかったことへの負い目を感じたり、体験してきたことが思い出したくない過去として記憶に残ってしまうかもしれません。

どちらが良い悪いではなく、続ける選択「も」あり、やめる選択「も」ある。
そう捉え、どちらも「選択できる」という視点を持つことだなって、上記を本を読んで思いました。
さあ、あなたはどちらを選びますか?
【私の体験談】「逃げてもいい」と自分に許可するまで

実は私、「やめる」決断がなかなかできなかったことがあるんです。
冒頭にも書きましたが、そもそも私はどんなことも「やめる」ことは苦手な方でね。
長く勤めた仕事を辞めるかどうか、むちゃくちゃ悩んでいた時期があったんです。
仕事内容はとても好きなものでした。それゆえに、やめる決断をすることがとても怖かったんです。
「やめたら後悔するんじゃないか」「今まで頑張ってきたのに…」「新しい仕事を探すのは大変だ」という思いが頭を駆け巡りました。毎日毎日、やめようか、続けようか、そればかり考えてました。

でも、一番私を苦しめていたのは「逃げるな」という自分自身の声でした。
「逃げても、また同じ問題にぶつかる」「逃げることは弱いダメ人間のすることだ」「問題にたちむかえ」。そんな厳しい正論を、私は自分にぶつけていました。
でも、思い切って「やめる」という選択をしたとき、初めて自分の本心に気づいたんです。
「ああ、私は逃げたかったんだな・・・」。
それを自分に許可できなかったのは、
「やめる=逃げる=ダメなやつ」という恐れがあったこと。
「頑張れる場所」を失うことへの恐怖。なぜなら、「頑張ること」が私の存在証明だと思っていたからです。
自分に許可を出して「やめる」経験をしたことで
自分の中にあった多くの思い込みや前提、自分で自分に大きな縛りをかけていたことに気づきました。それは「やめなければ」見えなかったものです。
「逃げる」が良いとか悪いとかではなく、それらに気づくために、そして許可を与えるために「必要な出来事」だったと、今はそう思っているんです。

「続けること」を大事にしている私たちだからこそ、「やめる体験」には大きな意味があると思っています。
「やめない」という能動的な決意と、「許す練習」
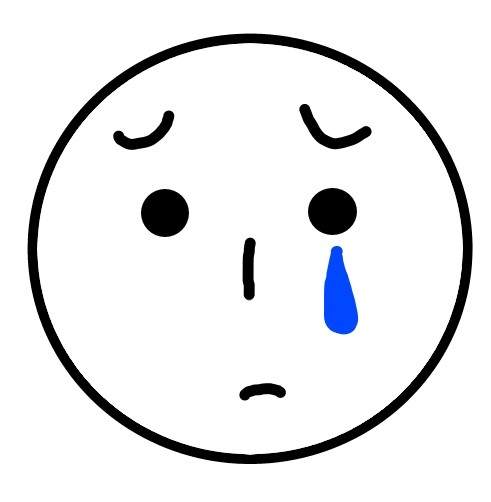
うん・・・なんとなくわかってきた。それでもな・・・
それでも、「やめる」ことは怖いし迷いますよね。長年信じてきた「続けること」の価値観を、そう簡単に手放せるものではありません。
では最後に、それでもやっぱりやめるかどうか迷うなら、以下の2つことを試してみてください。

①「やめられない」のではなく、「やめない」という能動的な思いとして現状をとらえる。
現在の状況を「自分で選択しているのだ」と思うか、「無理やりそうさせられている」と思うか、そこには大きな違いがあります。
自分の意志で「あとこれだけ頑張ってみる」と能動的に決意できれば、たとえ後で後悔したとしても、納得できるはずです。

②「許す練習」もしてみよう。
「我慢の練習」をしてきた私たちは、どうしても自分に厳しくなりがちです。だからこそ「許す練習」も「やめる練習」とともに必要だと思うんですよね。
- 「ああ、やっぱりやめられない…」→ 許す!
- 「ああ、また頑張ってしまった…」→ 許す!許す!
- 「ああ、続けられない…」→ それも許す!許す!許す!とことん、許す!
「やめる練習」をしてきたマレーシア人は、自分にも他人にも優しいと言いました。
それは、自分にも他人にもたくさんの許可を与えているということです。そのマインドを取り入れるんです。
ただただ自分に優しくするだけ。どんな選択をしても、全部許す。許さないことには、練習なんて続かないですからね。
まとめ
- 「やめる」ことにマイナスなイメージがあるのは、「やめる=逃げる=ダメな人」「大変なことになる」という「恐れ」という思い込みがある
- 「続ける」ことは大切なことだが、唯一の正解ではない
- マレーシア人の人生観「ハッピーじゃなければ居場所を変える」それは自分にも他者にも優しい社会
- 「続ける」も「やめる」も選択肢のひとつである。どんな選択も「恐れ」を前提にするのではなく、ニュートラルにしたうえで選択する
- それでも「やめる」ことに対して恐れがつきまとうなら・・・・
「やめられない」じゃなく、「やめない」選択をしているのだという能動的な視点をもつ - 「許す練習」も積んでいく。