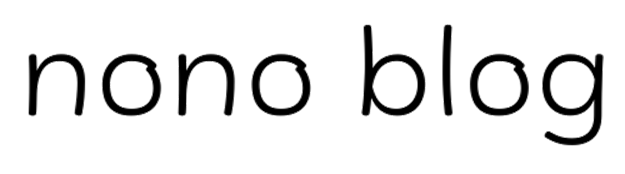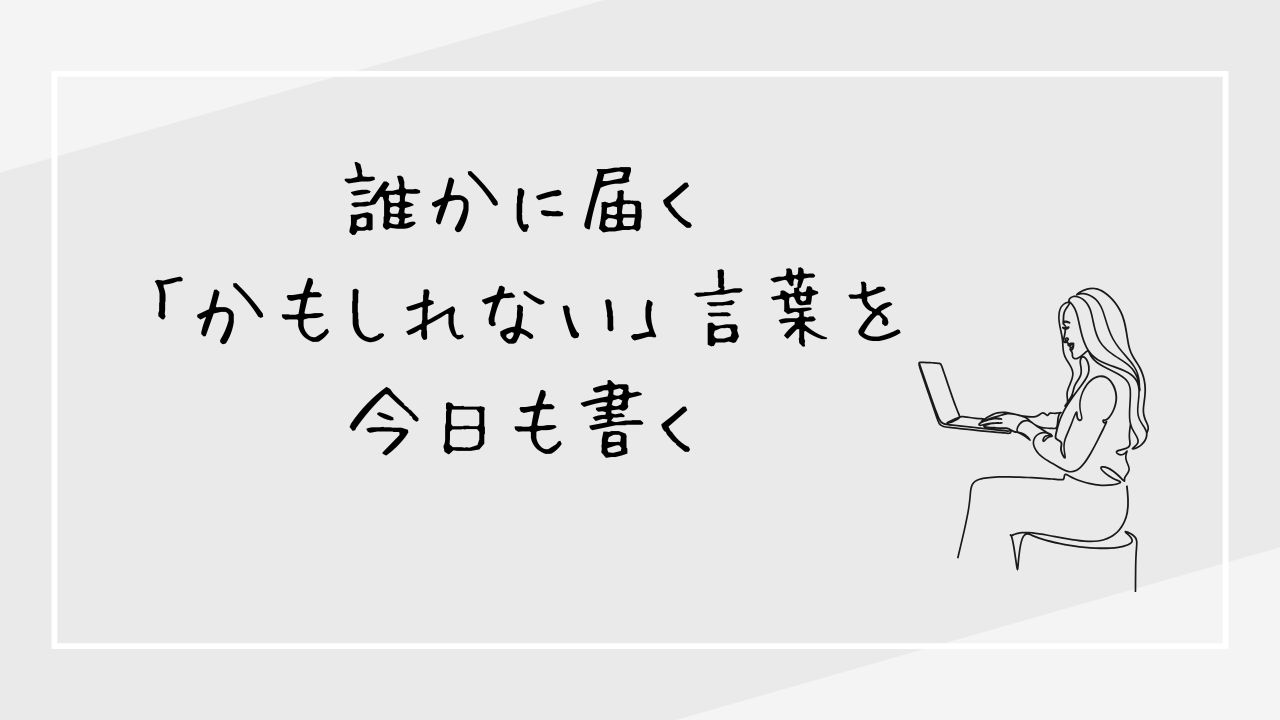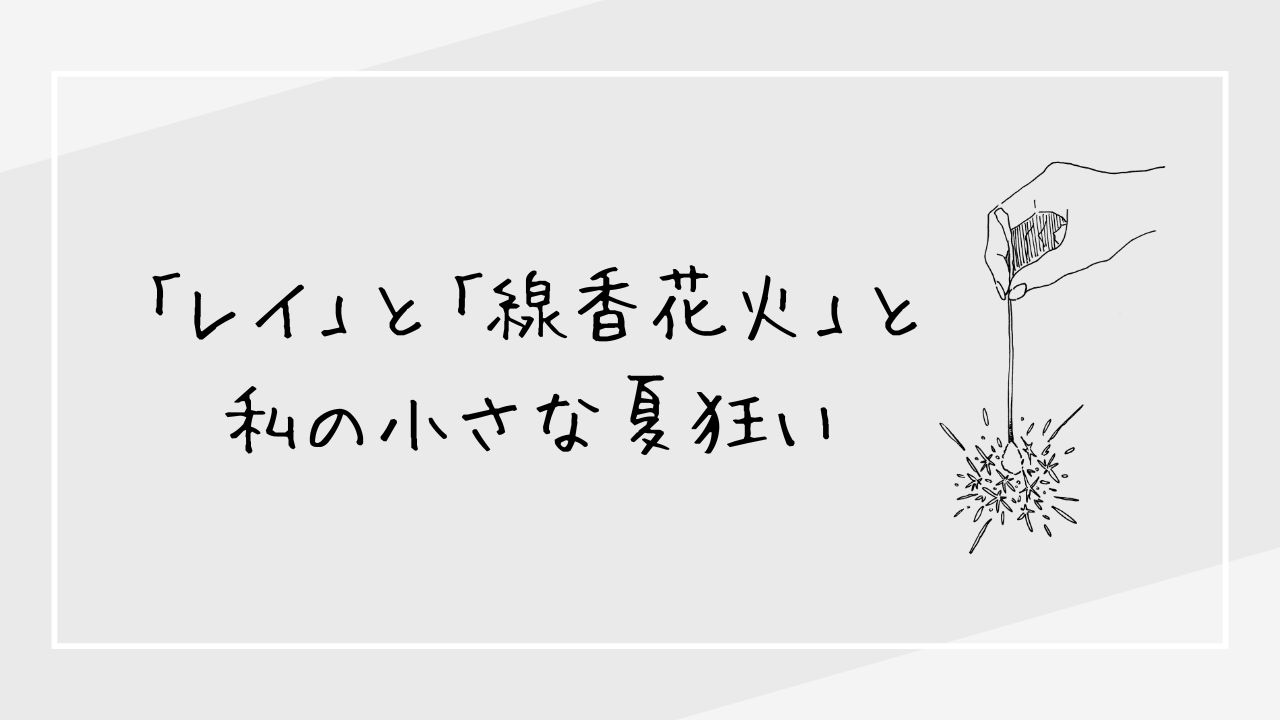ブログを書きながら、いつも思うんです。
「ああ、もっと気楽に書けたらいいのに・・・」。
ブログを始めてから、その思いはどんどん強くなってきたんですよね。
書きたい気持ちはあるのに、どこかで自分を縛ってしまう。
「たくさんの共感を得られるように書かなきゃ」とか、「人を感動させる文章にしなきゃ」とか。
そんな思い込みが、いつも頭の片すみにあって気楽に書けない。
それなりにブログの勉強もしてきたし、文章術の本も何冊も読んできた。
今回読んだ『読みたいことを、書けばいい。』も、そんな思いから手に取った一冊でした。
でも最初にこの本のタイトルを見たとき、正直「はいはい、自由に書けばいいってことでしょ」と思ったんですが、この著書の「はじめに」を読み終えた瞬間、「好きなように書く」ってこういうことなんだ〜と、体感でわかった気がしたんです〜。

もうこの「はじめに」で、本を閉じてしまってもいいくらい(笑)
「あなたはゴリラか?」の一文にこめられた自由さ
著者が中学生だった頃、ある雑誌に「職業適性診断Yes Noチャート」というえものがあって軽い気持ちで試したんですって。その最初の質問が「あなたはゴリラか? 」というヘンテコな質問だったらしい。
何を考えているんだと思いながら「yes」を選び先へ進むと「あなたはゴリラだ。まず人間になることを考えよう」と。(笑)
このエピソードを読んで、私は声を出して笑ってしまった。こういう感覚、めっちゃ好き。
そして著者はここで気づくんです。
「この診断を作った人は、きっと自分が書きたくて書いたのだ」と。 命令されたわけでも、求められたわけでもない。自分が楽しかったから、書いたのだ。

ああ、そうか。「自分が楽しい」ってこういうことか。
「自分が書きたいもの」「自分が読みたいもの」を書くって、こういうことなんだって、その瞬間、腑に落ちたんですよね〜。
書くことは、テクニックより「考え方」
この本は、テクニック本ではなく「書くとはどういうことか」を教えてくれます。
ここで著者の経歴を少し。
1969年に大阪生まれ。広告会社である電通で24年間コピーライターとして勤務。電通をやめる1年前くらいから「街角のクリエイティブ」というwebサイトに『田中泰延のエンタメ新党』というコーナーで映画評論を書いていて、それが大きな反響をよんでいたそうです。
最近は誰もが自由に発信できる時代になって、「バズる記事を書きたい」「誰かに響く文章を書きたい」。そしてそんな思いの裏には、「認められたい」「成功したい」という欲が潜んでいたりする。(ええ、私も(笑))
でも、著者は言うんです。
そういう気持ちで書いた文章は、結局読まれない、と。
たとえば、よく言われる「読者ターゲットを明確に」や「たったひとりの人に向けて書く」というのにも、著者はあっさりこう言いきります。
「それならLINEしてください」
電通での仕事はまさしくターゲットが明確にされていた世界。でも、結局それらもテレビなど不特定多数が目にするところ に「置かれる」のであり、「届けられる」のではない、というんです。特定の誰かに「届ける」ということがいかに難しいか。
そして、どんなに思いをこめて時間をかけて書いたって、誰かに読まれる保証などはない。それはなぜか。
あなたは宇多田ヒカルではないからである。
(笑)
つまり、多くの人は「何が書かれているか」よりも、「誰が書いたか」で読むかどうかを決める、と。それが現実なんですよね〜。

だからこそ、著者は声を大にしてこう言います!
「たくさん読まれたい」「ライターとして有名になりたい」という下心を捨て、まず、自分が書いた文章を自分がおもしろいと思えれば幸せだと気がつくべきだ、と。それを徹底することで、逆に読まれるチャンスが生まれる、と。
たとえ誰にも読まれなくても、まず自分が面白いと思えるかどうか。自分の書いた文章を読んで、自分で少し笑う。文章を書くというのは「 誰かのために」ではなく「自分のために書く」ということ。それが「書く人」の生活なのだ、と言うんですね。
おもしろさの出発点は、〈事象 × 心象〉
今、世の中に出回っている多くの文章は「随筆」だと著者は言います。随筆とは「事象(見聞きしたこと)」と「心象(心が動いたこと)」が交わる場所に生まれる文章のことだと定義しています。
じゃあ著者が書く随筆の具体的な方法はどういうものかというと、お題に対してまず調べる。ネットの寄せ集めではなく、図書館などを利用して本当の「出所」をたどり、そこでなにを感じるか。9割調べて1割自分の思いを書く。
いやいや、私の思いをもっと書きたい!表現したい!という人には
歩道橋で詩集を売ろう
だそうです。(笑)

私はもっと自分の思いを書きたいけどな〜
宇多田ヒカルじゃない私たちが、自分のために書くには
読み終えて思ったのは、
著者は自ら書きたいと思って書いてきたわけじゃないんですよね。いつも依頼があって、仕方なく書いてきた。だからこそ、どうせ書くならイヤイヤ書くのではなく、少しでも楽しく書くために、依頼されたお題の中に「愛すべき箇所」を見つける。そのために調べまくる。そしてそこで感じたことを書く。そう、自分で読んで楽しいものをね。
ただ私も含め、ブログなどを書いている人は、自分が書きたいから書いている人が多いんじゃないでしょうか。
そしてそこには、自分の思いを1割じゃなく、もっと書きたい。(って、私だけ?)
こういう本を読むと、「そうか、ちゃんと調べて書かなきゃ」とか、「著者のように書かないと読まれないのか」と思ってしまう。でも、それってまた「誰かのため読まれるために書こう」としている自分に戻ってしまう気がするんですよね。
宇多田ヒカルではないので(笑)、多くの人に読まれることはおそらくないだろうけど、でもやっぱり誰かに読んでほしいじゃないですか。思いをこめて書いたものだと、より一層そう思ってしまう。思うなって言われても思ってしまうのが人間っていうか。庶民っていうか・・・平民っていうか・・・(笑)
ただそれだとすぐに「自分のために書く」ことを忘れてしまう。
だからだから!忘れて書くことがつらくなったときこそ、冒頭の「あなたはゴリラか?」の自由さを思い出したい。その「原点」に帰れば、また書くことが続けられそうな気がしました。
著者が、電通をやめた理由として、こうなふうに語っていたんです。
自分の中で、やれといわれてもしたくないことと、やるなといわれてもしたいことがはっきりしたから、生き方を変えただけなのだ
書くことは孤独で、めんどうで、しんどいこともある。
でもそれでも書きたいと思うのは、自分のために書いたものが、たまたま誰かの心に届く(かもしれない)・・・その瞬間に、つながりが生まれる(かもしれない)・・・(笑)
と、性懲りもなく、やっぱり誰かに読まれますようにという期待をほんのちょっとだけもって、自分のために書く。それが私の中で「やるなと言われてもしたいこと」として、書く原動力にもなっているんだと思います。
まとめ
- 書くのは、誰かのためじゃなく、自分のため。自分が楽しいと思えることを書こう
- 書くことに疲れたときこそ思い出したい「あなたはゴリラか?」

そして、ちょっとぐらい「読まれたい」欲があってもいい、それが書く原動力にもなる!