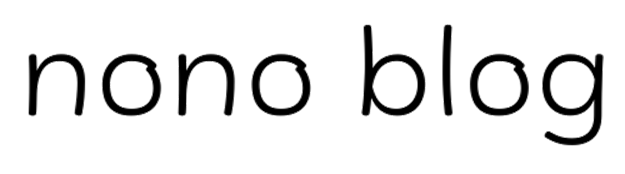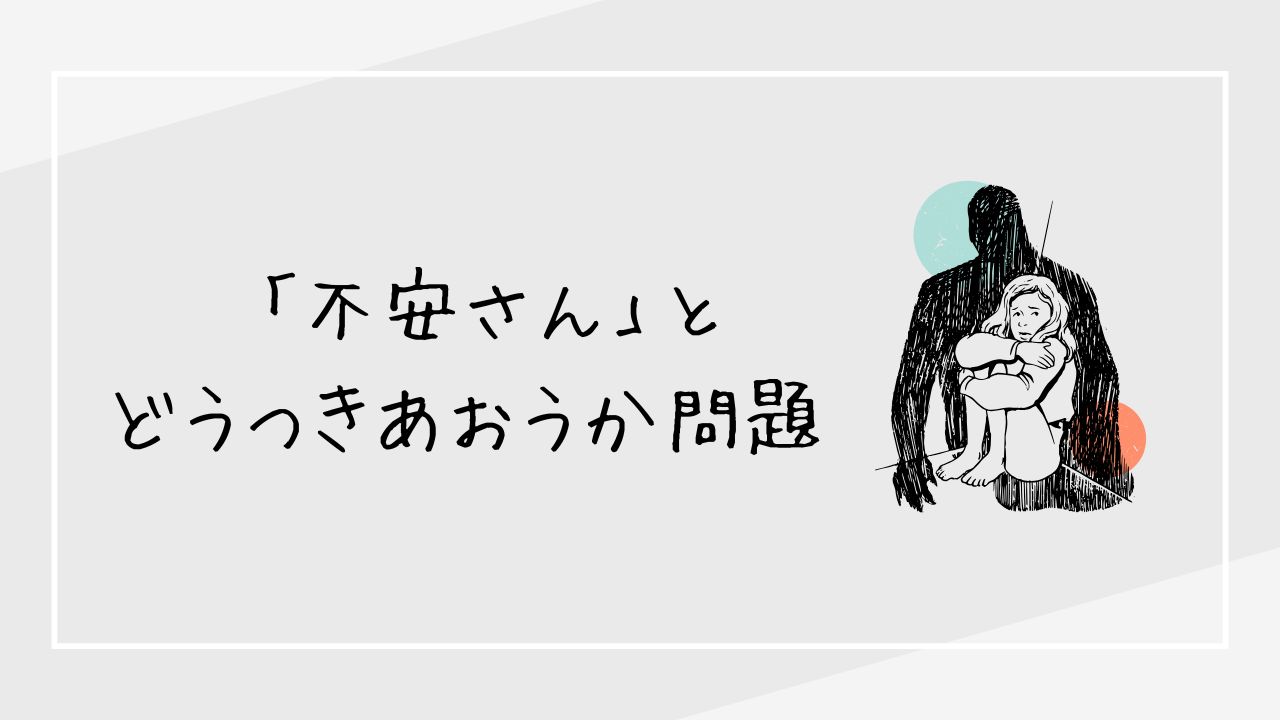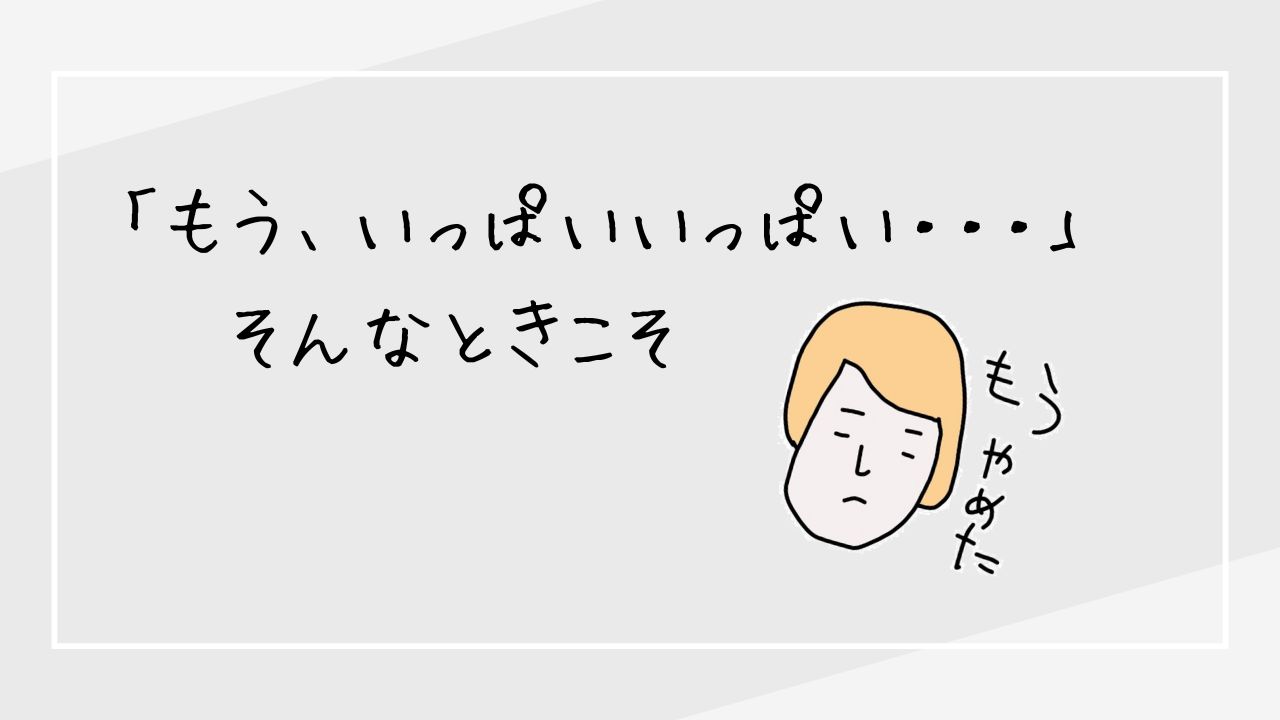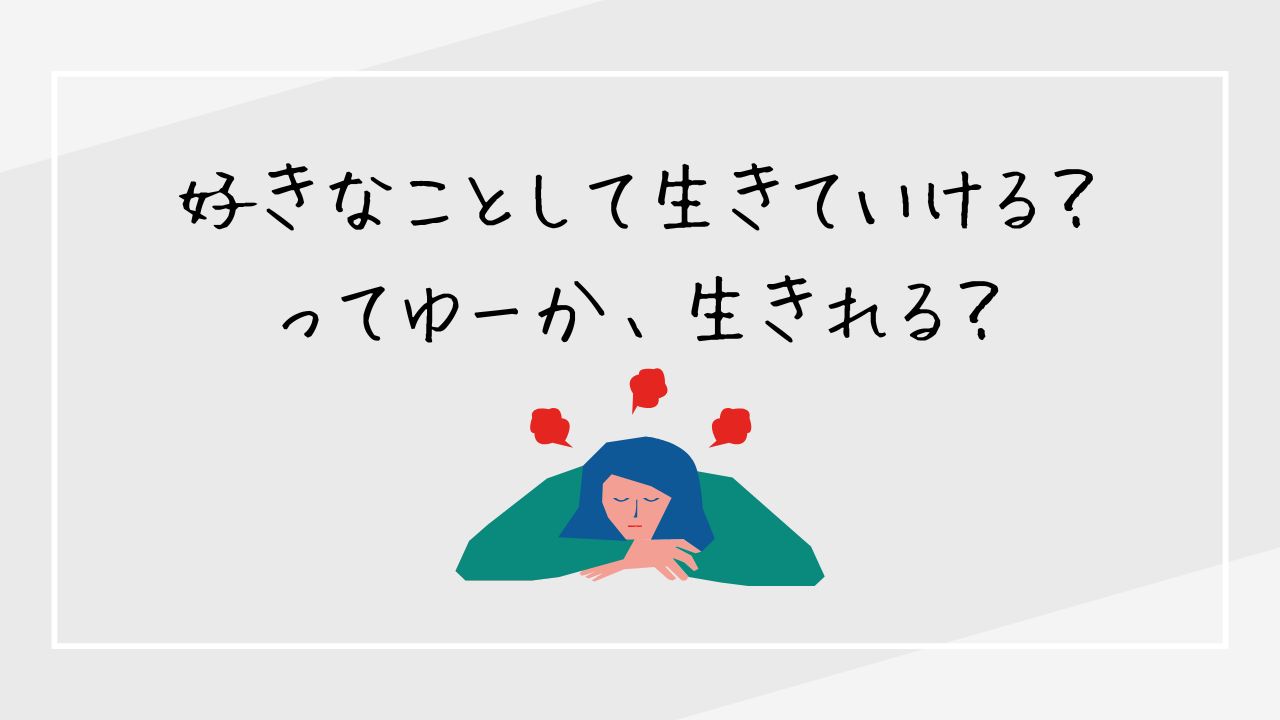「こうなったらどうしよう…」「あれがうまくいかなかったら…」
自分のこと、家族のこと、仕事のこと、将来のことetc、夜眠る前やふとした瞬間に、そんな不安な思いが頭の中を駆け巡り、まるで終わりのない迷路に迷い込んでしまったような気持ちになったり。
体調が優れない時や、何をやってもうまくいかない時などは「この状態がずっと続くのではないか」という絶望的な気持ちにさいなまれたり。
どうしたらこの不安がなくなるんだろう・・・。この不安さえなくなれば、もっとハッピーになれるのに・・・って、そんなふうに思ったことはないですか?
もし、少しでも共感できる部分があるなら、ぜひこの先を読み進めてみてください。
今回は「不安との上手な付き合い方」について、私自身の視点を交えながら綴っていきますね。
「さみしい」を埋めるために生きてきた著者
こんな本を、読みました。
この本の中で、著者は自身の不安を「不安さん」と名付け、「はたらく」をテーマに「不安さん」と格闘する日々をショートストーリーの漫画仕立てと心に響くエッセイで描かれていました。
不安な気持ちになることが多い私にとっても、どれもこれも「あるある」なことばかりで、とても共感できるものだったんですね。
著者は、20代で正社員として働き始めたものの、夢を追いかけて転職した広告デザインの職場で人間関係に悩み、退職。
その後、結婚して専業主婦になったんですが、著者はこんなふうに思いながら日々を過ごしていたそうです。
毎日、何をすれば、充実した一日になるのかという不安さんのジャッジが入ります。
充実して生きなければならないと、不安さんが言うのです。
(中略)せっかく自由にできる一日があるのに、自由が恐ろしかったのです。

この気持ちに共感できる人、けっこう多いんじゃないでしょうか。
「ダラダラしちゃいけない」「充実した日々を、人生を、生きないといけない」と、私たちは生産性のないことに無意識にダメこととしてジャッジしてはいませんか?
著者はそんな時間があると、全細胞が「さみしい!」と叫ぶように感じたそうです。
だから、その寂しさや不安を感じないように、いつも予定をぎっしりと詰め込んでいたと。
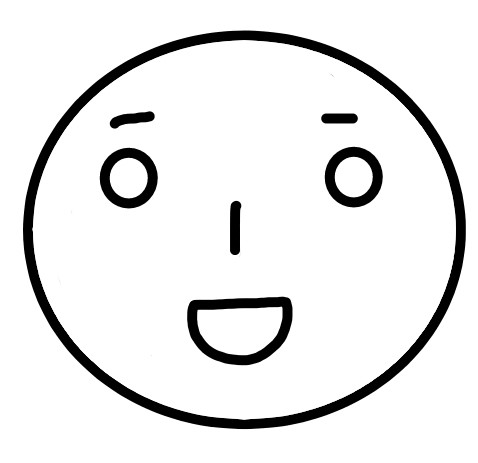
あるあるだ~
あらゆる選択肢を否定する、しつこい「不安さん」の声
たとえば、ある日の「不安さん」の声。
働いていないと、「不安さん」はこう言うのだそうです。
「働かないの?」
働こうと思うと、不安さんはこう言うんだそうです。
「またいじめられるかもよ」
何をしても、常に「不安さん」の声がする。
非正規雇用として働きはじめるんですが、すると「何もしない」ことの不安は小さくなってきたけど、今度はまた別の「不安さん」の声が出てきたんです。
たとえば、「有給とりたい」と思うと、「不安さん」は言います。
「嫌われるぞ」「迷惑かけるぞ」「クビになるぞ」
休みが終われば
「明日から仕事だぞ」
どれもこれも
「●●しないと大変なことになるよ」「●●すべきじゃないか」「あなたがダメだから●●になる」「そんなことしたら嫌われるよ?」と、ことごとく否定してくる「不安さん」。
でも、こうやって不安さんの声を視覚化すると、「もう、うるさーい!」ってその声を無視したらいいじゃんって思いません?

でも、不安の渦中にいると、そんなことには思えず、その声に振り回され動けなくなってるんですよね。
著者は「現状維持がいちばん」だと言います。
それは、変化することは、もし間違えば悪い方向へ進むかもしれないという「もしも」の声の方が大きく、自分の本当の気持ちに気づけなかったと振り返ります。
私たちの脳は、新しい変化に抵抗する本能を持っています。でも、それが強すぎると、行動することや変化を起こすことに、大きな恐怖を感じてしまうんですよね。
「不安さん」との共存。「いない方が幸せ」からの気づき
そんな著者は、自分と同じ悩みを抱える人たちが集まる「自助グループ」に参加するんですね。
そこで初めて、「不安に振り回されているのは自分だけではない」ということに気づき、「不安はなくならない」「不安はコントロールできない」ということを学んでいくんです。
そして、自助グループの仲間に支えられながら、不安をなくすのではなく、「不安との付き合い方」を身につけていきます。
そして、こうたどり着きます。
私は不安さんと共に、生きる決意をした。
かつて、「不安さんさえなければ、私は幸せになれるのに」とずっと思っていた著者。
しかし、それは間違いだったと気づきます。不安さんは、彼女が幸福になるように、安全であるように、最大限アンテナを張ってくれている、彼女の大切な一部。だからこそ、不安さんすら愛してあげたいと。
たくさん傷ついてきたから
読み終えて思ったのは、不安という感情は、著者の言うように私たちを守ってくれるもの。自己防衛本能であり、それは誰もがもっているもの。
でも、その防衛本能が過剰に働くと、まるで足かせのように私たちを縛り付け、身動きが取れなくなってしまうことがあるのも事実だと思うんです。

不安が大きすぎるのは、それだけ「傷ついてきた」ってことだと思います。
私たちは、幼い頃は誰しも自分の心の声にしたがって、もっと自由に生きていたはずです。
でも、その心のままに生きていたら、たくさん傷ついた。傷つけられた。
だからもうこれ以上、傷つかないように、不安という形で、私たち自身が自分を守ってくれているのかもしれませんね。
不安はなくならない。ならば、不安を力に変える!
著者は、不安さんを漫画やエッセイにすることや、自助グループで支え合うことで不安とうまく付き合っています。
生きている限り、不安はなくならない。
だとしたら、上手な不安とのつき合い方をたくさん身につけることが、不安とともに生きることを可能にすると思いました。
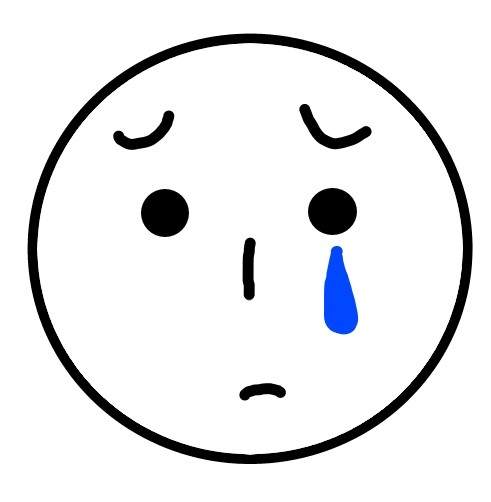
どうすればいいの?
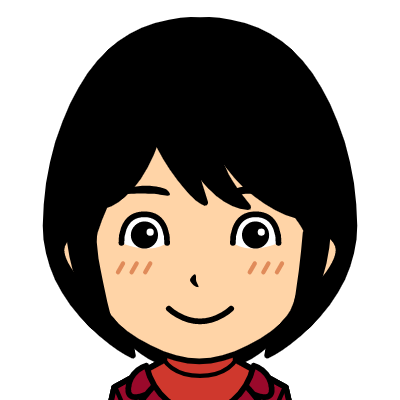
「不安があるからこそ」気づけることもある、という新しい視点をもつ。
例えば・・・。
●共感力が深まる
自分が不安を感じてきたからこそ、他者の不安のサインに気づきやすくなり、言葉にならない心の叫びを察知できる。相手の気持ちを理解しようと努め、心に寄り添う共感的な言葉をかけられるようになる。
●準備力を育つ
新しいことに挑戦する際には、 入念なリサーチを行ったり計画を練ったり、リスクを事前に予測し
何度も練習を重ねたりと、万全の準備をすることで本番での成功に繋げることができる。 それが結果として自信を生み出し、不安を軽減する効果も期待できる。
●自己理解が深まる
不安は、心のメッセージ。自分の内面と向き合うことで、これまで気づかなかった自分の価値観や欲求に気づくことができ、自分の弱点や繊細さも含めて、より自分らしい生き方を見つけるきっかけになる。
みたいな・・・。
不安は、私たちを守ろうとするサインでありながら、「不安があるからこそ」という視点を持つことで、これまでネガティブに捉えがちだった感情が、意外な力や可能性を秘めていることに気づかされませんか。
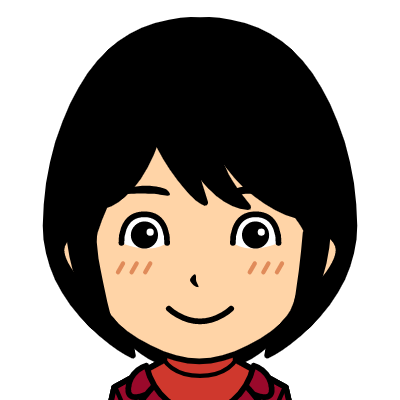
それらは、私たちが生きていく上で、とても大切な力になるはずです。
まとめ
- 不安は誰にでもある感情。自己防衛のための本能的な反応である
- 不安の大きさは、それだけ「傷ついてきたから」
- 不安を敵ではなく、共に生きる「仲間」として捉える。不安とうまくつきき合っていくことが大切
- 「不安があるからこそ」の視点を持つ。共感力、準備力、自己理解など、ポジティブな側面もあり、それは生きていく上で大切な人間力につながる