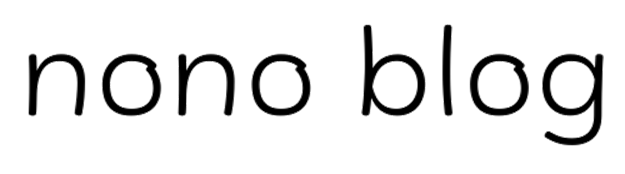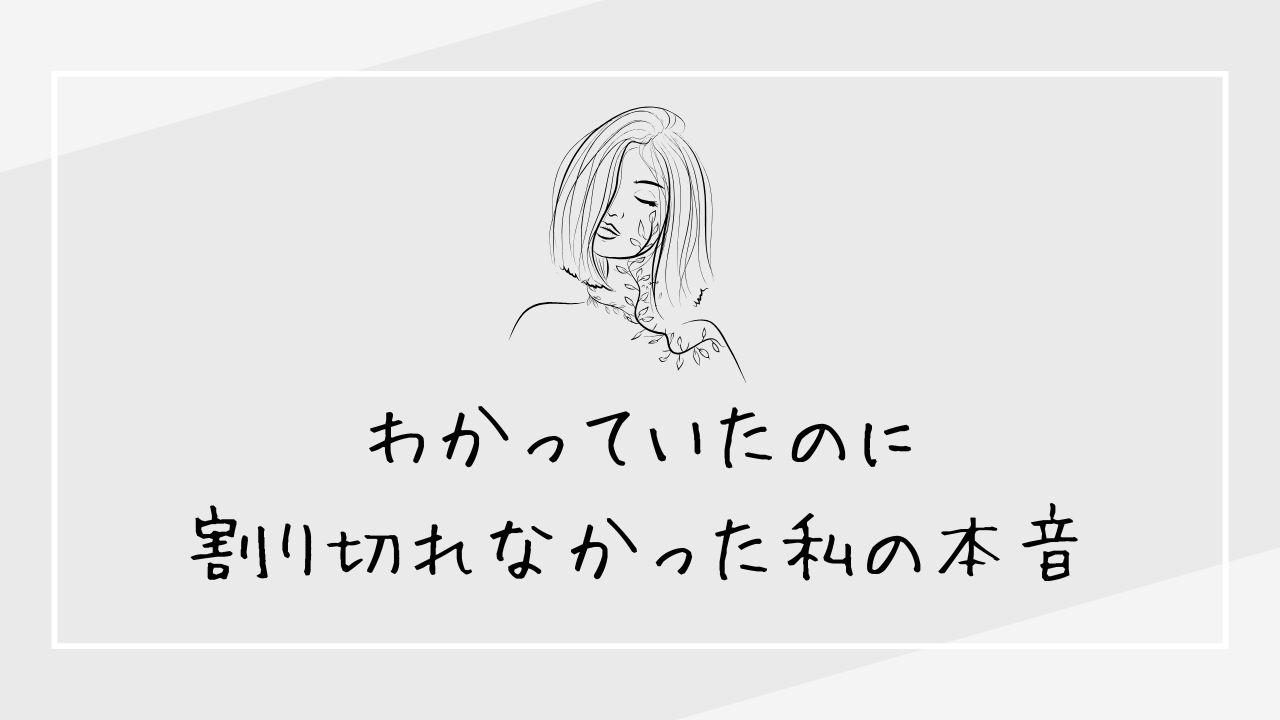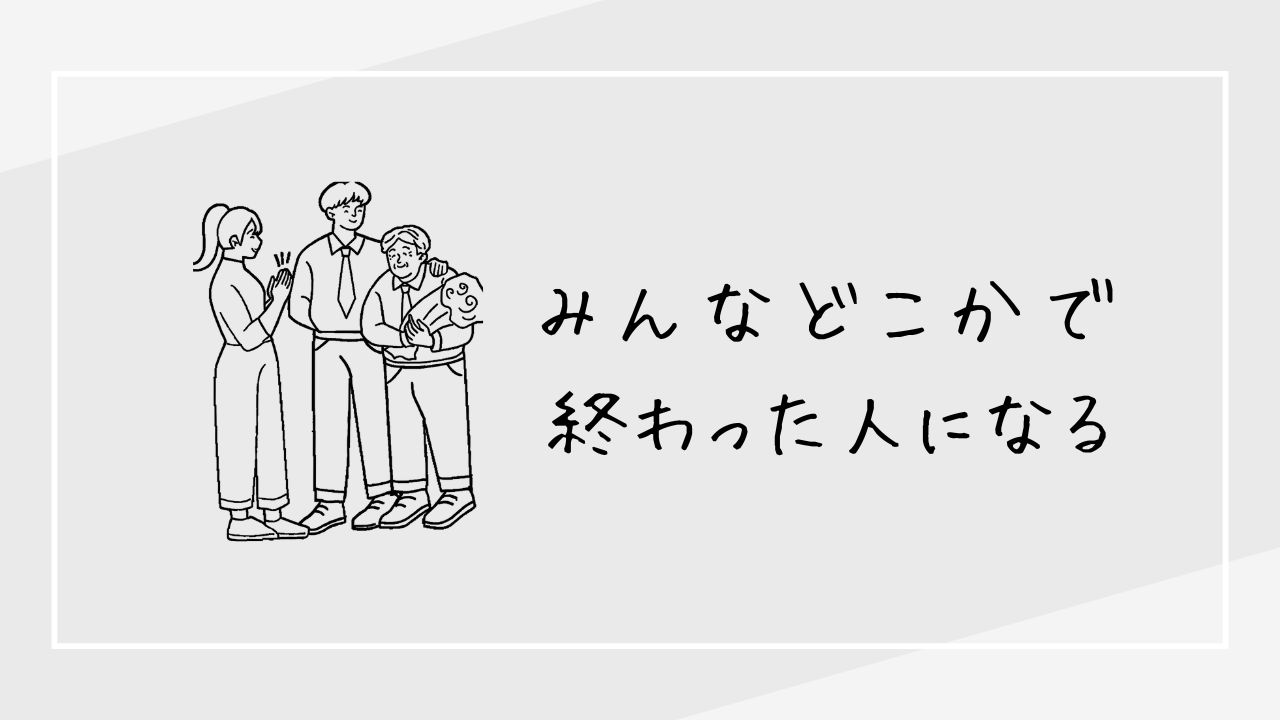皆さんは、石飛幸三さんという方をご存じでしょうか。
『平穏死』について書かれた書籍があり、私も何冊か読みました。
石飛さんは、在宅医療の第一人者として、そして特別養護老人ホームの医師として長く勤務され、自然な形で最期を迎える「平穏死」の普及に尽力された方です。かつて私は、先生の著書を読み深く共感たのを覚えています。
先日、ある人のブログで石飛先生が昨年お亡くなりになっていたことを知りました。私の両親と同じくらいの年代だったこともあり、非常に残念に思ったと同時に、こんなことを思い出したんです。

今は亡き父の最期の記憶です。
今日は少し個人的な、そして少し湿っぽいお話になるかもしれませんが、もしよろしければ、最後までお付き合いくださいね。
石飛幸三さんの「平穏死」
石飛さんが主張されていた『平穏死』という考え方。
それは、人生の終末期を迎えた高齢者に対し、過度な延命治療を施すことは、必ずしも本人のためにならない、むしろ苦痛を与えてしまう場合があると言うんです。
特に「胃ろう」について言及しておられ、自然の摂理に従い、食事が摂れなくなってきたならば死期が近づいている証拠。無理強いせずにそのまま静かに見送ることは、その人にとって穏やかな最期になる、いうものでした。
私がその本を読んだとき、とても共感していたんですが・・・

いざ自分の父の最期が近づいてきたとき、とてもそんなふうに割り切ることなんてできませんでした。
父の衰弱 – 理想と現実のギャップ
父は晩年まで健康に気を配り、毎日欠かさずウォーキングをしていた人でした。
ところが、ある日、そのウォーキング中に転倒してしまったんです。
その日から、父の体調は徐々に、しかし確実に崩れていきました。
食欲は衰え、食べる量も減っていきました。それにつれて体力も失われ、ついには寝たきり状態に。母は介護しきれず、病院へ。
そこで医師から告げられたのは、「腎臓が弱っている。透析が必要かもしれない」ということでした。
母は「積極的な延命治療はしなくていい」と伝えましたが、一緒にいた私は思わず母の言葉をさえぎり、「もう少し考えようよ」って伝えました。
生前、父も母も延命治療はしなくていいっと言っていたし、石飛さんのいう「平穏死」のことも頭ではわかっていたけれど、いざ、その状況になったら、とてもそんなふうには思えなかったんです。
どんなに高齢だろうと1日でも長く生きてほしい、それが家族の、いや、私の正直な気持ちだったんですね。
石飛さんは、そういう「生きててほしい」という家族の思いは「エゴ」だと言います。
でもでも、その時の私は、たとえエゴだろうとなんだろうと、父を失うことのほうがよっぽど辛かったんです。

エコでもいい、生きててほしい。ただそれだけでした。
揺れる家族の思いと、父の最期の言葉
弱りつつある父でしたが、意思疎通はなんとかできていたので、透析について父の意思を確認してみよう、ということになりました。
そして、父は絞り出すように小さな声で言ったんです。
「やってもいいよ」って。
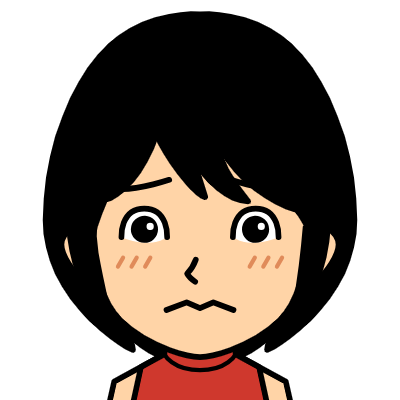
やってもいいって、どういう意味?
本当はやりたくないけど、仕方ないから「やってもいい」?それとも、わずかな希望に託して「やりたい」という気持ちの「やってもいい」?
私の頭の中は混乱し、様々な思いが交錯しました。そうこうしているうちに、父の容態は急変し、結局透析を行うことなく、父は息を引き取りました。
父の死を受け入れられなかった日々と、石飛さんへの問いかけ
父は本当はどうしたかったんだろう・・・。
気持ちの整理がつかないまま時間がたち、なかなか父の死を受け入れることができなかった私。
そんなとき、偶然にも地元で「平穏死」を語られている石飛さんの講演会があるのを知りました。迷うことなくすぐに申し込み、会場へと向かったんです。

父への思いを振り返りながら、最後の質疑応答で勇気をもって質問したんです。
延命治療について母との意見の食い違い。私は1日でも長く生きてほしかった。
最期の父の「やってもいいよ」という言葉は、どういう意味だったんだのか。
私が父の最期に対して納得できなかったことを、全部石飛さんにぶつけました。
石飛さんは、私の質問に耳を傾け、穏やかな口調でこう答えてくれたんです。
「お父様は、もう、どこか諦めにも似た、投げやりな感じで『やってもいい』と言われたのではないでしょうか。そして、結果的にお母様が望まれていたように延命治療をすることなく事が運んだ。それが答えだったんではないですかね。」
少し記憶が曖昧ですが、確かそのような趣旨の回答だったと記憶しています。
その回答を聞いて、なんとなく私の中で「ああ、あれでよかったんだ」と思うことができたんですね。かすかな安堵感というか・・・。
「やってもいいよ」の父らしい思い
父が亡くなって、もうずいぶんと時間が経ちました。今は、ようやく穏やかに思い出せるようになっています。
そしてふと、あの「やってもいいよ」を振り返ると
自分の死期をうっすら感じ取っていただろう父。「俺のことはもういい。お前たちがそう思うなら、そうしてもいいよ。お前たちが納得する形を選べばいい」と、自分の気持ちよりも残される家族の気持ちを優先しようとしたのではないか。そんなふうにも受け取れるようにもなったんです。
それを「なげやり」と呼ぶなら、それでもいい。

でもある意味、父らしい言葉なんです。優しい人だったもんな~(涙)
こんなことがあったんです。
父が亡くなってちょうど四十九日目の夜、夢の中に父が現れてくれたんですね。
少し若い頃のふっくらとした体形で、なんとも穏やかな笑顔の父に私は駆け寄り、思いっきり抱きつきました。「お父さーん」と泣きながら・・・。
目が覚めたら、涙がこぼれてたんですよね。
でも、父はようやく安らぎの場所へ旅立てたんだなって、そんな気がしました。
時を経て思う―父の死を通して教えてくれたもの
父を見送って思ったのは、人には寿命というものがあるということ。
あんなに健康に気を配っていた父が、まさかウォーキング中で転倒するなんて思いもよらなかった。なんていうか、抗うことのできない大きな流れのようなものがあるんだなって感じました。
そして、人の最期について
石橋さんが言うように、逝くほうは「静かに旅立ちたい」と願うかもしれない。でも、見送るほうは、そう簡単には割り切れない・・・。
当時の私は「大事な人を失いたくない」そんな不安を落ち着かせたくて動いていたように思います。穏やかに送り出すなんて、とてもできなかった。ただただ、何かをしていないと怖かった。
気づけばそれは、石飛さんの言う「エゴそのもの」だったのかもしれません。これからだって、大事な人を失うときは、きっと同じ気持ちになるでしょう。
それは、人の死がきれいごとだけじゃ語れない現実があって、どんなに介護しても、もっとああすればよかった、こうすればよかったっていう後悔はぬぐえない。

そんなどうしようもない感情が渦巻く、どうにもならない人間の弱さを、親の死という経験を通して、父は私たちに教えてくれたような気がしました。
簡単に割り切れない。だからこそ、そこに深く残るものがある。
石飛さんの語る「平穏死」は、「どう逝くか」という正解を求めることより、人の最期に「どう向き合うか」の大切さに気づかせてくれるきっかけとなりました。
そしてもしかしたら・・・
私たち家族の戸惑いや迷いこそが、旅立つ人への供養になっているかもしれない・・・、そんなふうにもね。思うんです。
石飛幸三さんの訃報に触れ、あらためて父のことを思い出しました。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。