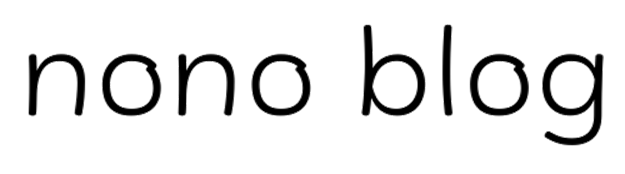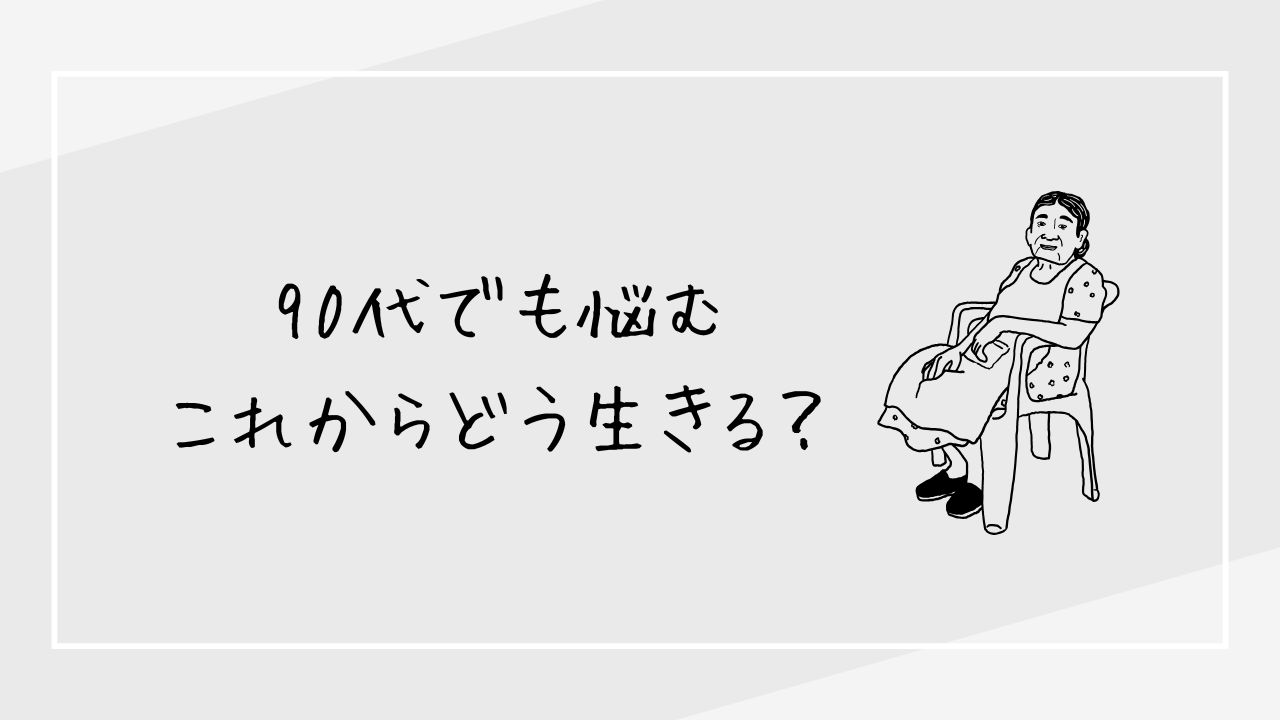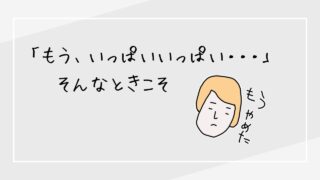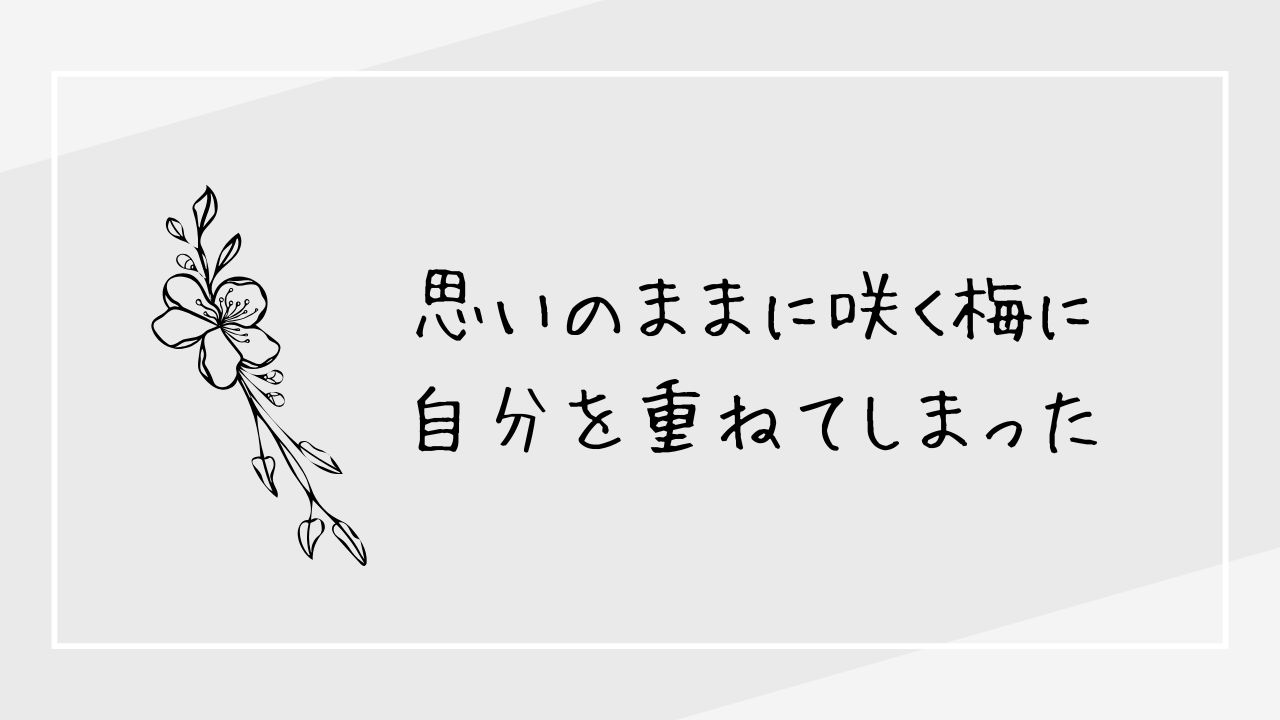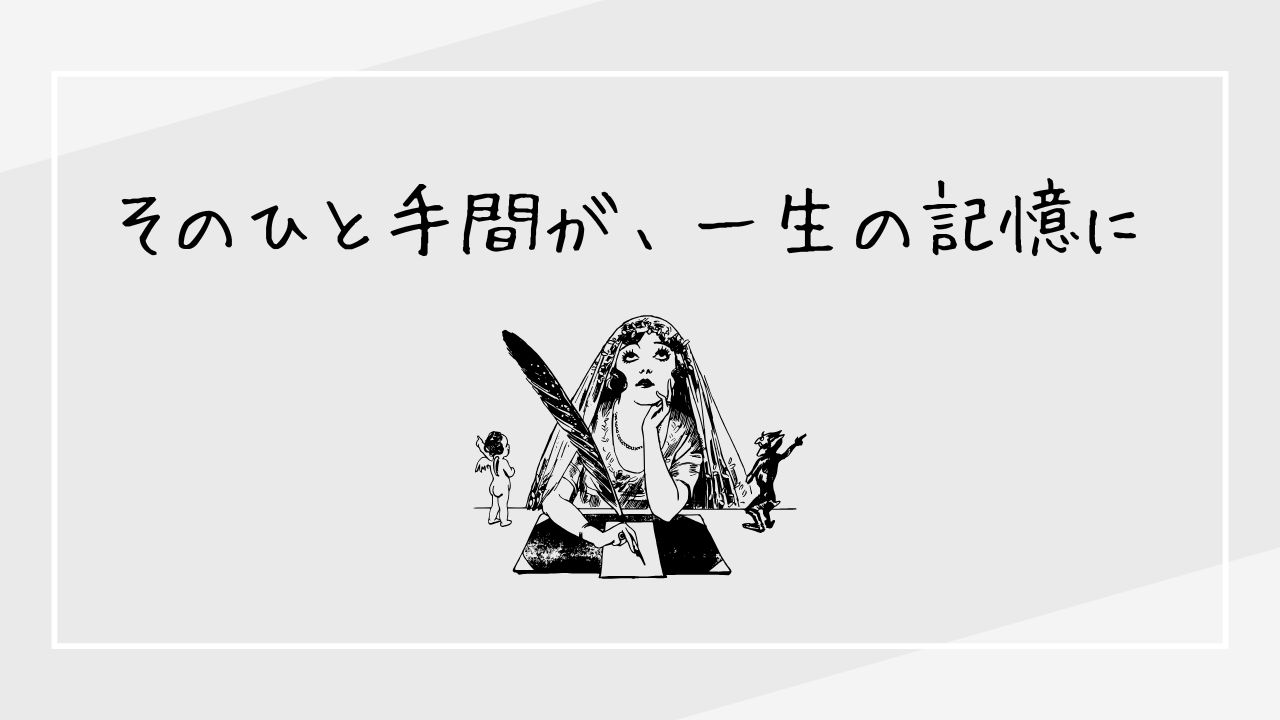随分前に観たNHKのETV特集「餅ばあちゃんが教えてくれたこと」という番組。ご覧になられた方はいらっしゃるでしょうか。
当時94歳(2022年時点)になっても現役で笹餅作り続ける桑田ミサオさん。その姿は、本当にパワフルで、見ているだけで元気づけられるようでした。
今日は、その番組を観て感じたことを綴ってみたいと思います。よかったら、読んでいってくださいね。
NHK ETV特集「餅ばあちゃんが教えてくれたこと」
笹餅づくりをされている 桑田ミサオさん ググってみると、2023年95歳で笹餅づくりを引退されたそうです。
番組は、2019年から2年間、そんなミサオさんの日常を追い続けたドキュメンタリーでした。
たった一人で年間5万個もの笹餅を作られていたこと。しかも、その笹餅は大変な人気で、店頭に並ぶとすぐに売り切れてしまっていたと、本当に驚きでした。
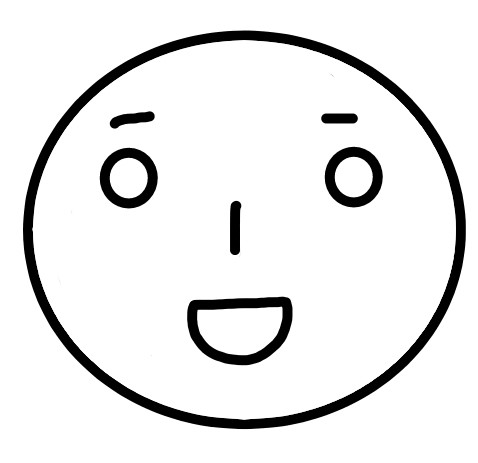
すごーい!食べてみたかった~!
ミサオさんが笹餅づくりを始めたきっかけは、60歳の時。老人ホームへ自分が作った笹餅を持って行ったところ、2人のおばあちゃんが涙を流して喜んでくれたそうです。その姿を見て、ミサオさんの心は大きく動いたんだそうです。
ミサオさんは言います、
今まではお掃除とか、与えられた仕事をして生きてきたけど、こんな私でも誰かを喜ばせることができるんだ、
そして、笹餅づくりを一生続けようと決めたらしいんです。

自分が誰かの役に立てたと思えたときってすごく嬉しいし、エネルギーもわいてきますよね
90歳を過ぎても、良い香りの笹を求めて軽快に自転車に乗り、小豆も自分で育て、丁寧に丁寧に丹精込めて笹餅を作るミサオさんの姿は、見ている私たちの心を強く打ちました。そして、何よりもそのお人柄が朗らかで、お肌もツヤツヤ、とても若々しくてチャーミングなのです。
好きで始めた笹餅づくりだが
2019年から続いていた取材は、コロナ禍で一時中断。2021年に取材班が久しぶりにミサオさんを訪ねると、彼女は笹餅づくりを辞めようかと口にしていたんです。理由は様々あったでしょうが、体力的なことが大きな要因だったように感じました。
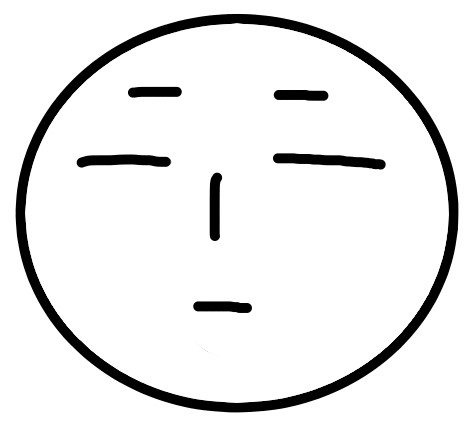
そりゃそうだ
しかし、それを聞いたまわりの人たちはこう言うんです。
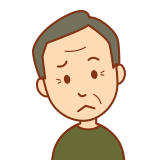
辞めるなって、辞めたらサビちまうよ
誰かに喜んでもらうことが嬉しくて作り始めた笹餅づくり。たくさんの人に喜んでもらい、それがミサオさんの生きがいだったはずなのに・・・・。番組の最後は、そんなミサオさんの葛藤が描かれていました。
いつまで頑張り続けなければいけないの?
ミサオさんの姿を見て、私は亡き自分の母と重ねていました。
当時89歳だった私の母は、電話で話すたびにこう言うのです。

どうせ死ぬんだから・・・
そんな母よりも年上のミサオさんが、母よりもずっと元気に見えるのは、きっとこの「笹餅づくり」があるからこそ。だから、周りの人がミサオさんにやめるなと止める気持ちは痛いほどよく分かりました。
私も母に対して、「あれをしてみたら?」「これをしてみたら?」と、なんとか生きがいを持ってほしくて色々アドバイスするのですが、

どうせ死ぬんだから、好きなようにしたい・・・
なげやりにも本音にも聞こえるその言葉に、私は何も言えなくなっていました。
で、同時に、ミサオさんを見ながら、こうも思ったんです。

私たちはいつまで頑張り続けなければいけないの?
なんでやめちゃだめなの? やめるやめないを、どうしてまわりが決めるの?
やめてはいけない、その奥に、
「何もしないのはよくない」「成長しつづけなければいけない」「生きがいをもたなくてはいけない」「生きがいをもたないと幸せではない」などなど
そんな大きな大きな思い込みがあるんじゃないかって・・・。
生きがいをもたないと幸せではないんですか?
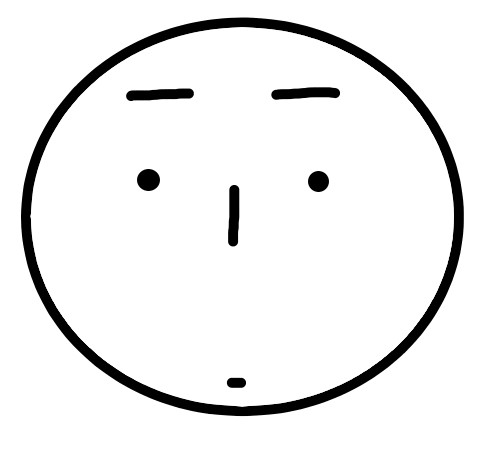
でも、生きがいはあった方がいいでしょ。
確かにそうですよね。そこに異論はないです。
ただ、「生きがいをもたなくては幸せではない」「何もしないことはよくない」などという思い込みがもしあるのなら・・・?それがかえって本人を追い詰めているとしたら?
好きで始めたことでも、好きで始めたことだからこそ、「辞めてしまっていいのか」と悩む。あるいは、周りの応援があるからこそ、その期待に応えなければと思ってしまう。期待に応え続けることって、想像以上にエネルギーを使うものだと思うんですよね。
葛藤するミサオさんは、番組の最後にこう言いました。

どうやって生きていったらええんかな・・・
94歳のおばあちゃんがこんなふうに言うんですよ。
人はいくつになっても、羨ましがられるような生き方でさえも、死ぬまで自分の生き方に葛藤し続けるものなのかなと、ミサオさんを見て思いました。
秋元康氏の説く「〇〇力」

この番組をみたあと、こんなことを思い出しました。
随分前に読んだ秋元康氏の本(なんていう本だかは忘れてしまいました)の中に、こんな言葉があったのが、とても記憶に残っているんです。
逃げるってことに関して「逃げずに乗り越えろ」という考え方もあるけれど、秋元氏は「逃げてもいい」と言うんです。逃げて、そしてまた心が回復して戻りたくなったら、戻ればいいって。大事なのは「戻る力」だと。
この言葉に、逃げてもいいし、また戻ってもいいんだって思えて、とてもラクになったのを覚えています。
何も失わない
今回この番組を見て、いくつになっても自分を必要とされることがあって、本人もそれを生きがいに感じている。それはとても幸せなことなのに、それでも葛藤ってあるんだと思ったんですね。
それは、今の状態を失うことへの恐怖や、期待に応えられない自責の念などがそうさせているのかもしれない。
だとしたら・・・
笹餅づくりをやめても、私の母が「どうせ死ぬんだから」と寝てばかりいても、それでもいいよと、やりたいようにやっていいよと、戻りたくなったらいつでも戻っていいよって。
それでも、何も失わない、価値も変わらない。
自分にも、そして他人にもそう思えたなら……現実はどう変わって見えるんだろうって思ったんですよね。
本当は、頑張り続けても、逃げても、どっちだっていいのに、「〇〇しなきゃ△△になる」という囚われが葛藤を生んで、本人も見てる私たちも苦しくなっているのかもしれませんね。
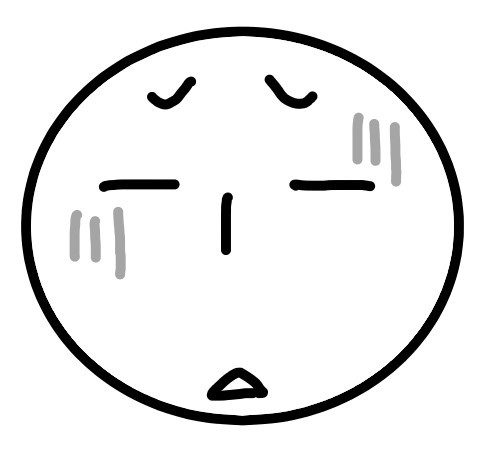
でもな~、なかなかそう思えないから苦しいわけで
ですよね~。そんなときは、秋元氏の言った「戻る力」が私たちにはあるんだと信じてみてもいいのかもって思いました。
まとめ
- 好きで始めたことでさえ、やめたい、逃げたい、でもやめられないのその奥に
「生きがいをもたないと幸せじゃない」「何もしないことはよくない」「期待に応えないといけない」などという思い込みがあるかもしれない。 - やめても、逃げても、また戻りたくなったら戻ってくればいい。「戻る力」が私たちにはある。